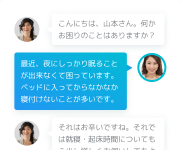子育て期の鬱。それは甘えではなく、誰しも発症する可能性があります。パートナーや家族の様子がおかしいことに気づいたら、あなたの支えが必要な時です。
この記事では、パートナーや家族が子育て鬱かもしれないと思ったときに、あなたがどのようにサポートしていけばよいかを解説していきます。また、支える家族が潰れてしまわないためのヒントもあわせてお伝えしていきます。
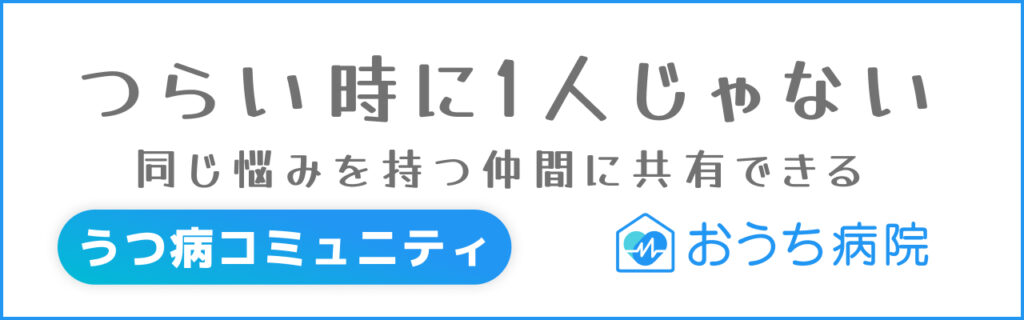
目次
子育て鬱のサインを見逃さないで
子育てをしていると、想定外の子どもの言動に振り回されるなど、初めて経験することの連続です。こういった心身の疲れの影響で、誰にでも子育て鬱になる可能性があるのです。
しかし、本人が「ちょっと疲れているだけ」「気のせいだろう」と思い込んでいて、なかなかSOSが出せない場合も多いです。パートナーの様子を気にかけてあげることが重要になります。
子育て鬱の主な症状
正式な診断名ではありませんが、一般的に子育てが引き金となる鬱病を子育て鬱と呼びます。心身ともに不安定になりやすい子育て期には、以下のような症状が出ることがあります。
子育て鬱かもしれないと思ったら、以下の心と体のサインをチェックしてみましょう。
心のサイン
- 笑うことができない、物事の面白さが分からない
- 何も楽しいことがない
- うまくいかないときに自分を必要以上に責める
- 理由もなく不安や心配になる
- 理由もなく恐怖感に襲われる
- やることがたくさんあって大変に感じる
- 悲しさや惨めさを感じる
体のサイン
- 不安や恐怖感などであまり眠れない
- 悲しさや辛さを感じて涙が出てくる
- 自分の体を傷つけたい衝動に駆られる
これらの症状が3つ以上当てはまるようであれば、子育て鬱の可能性があるため病院を受診した方がよいでしょう。また、3つ以上当てはまらなくてもどれか一つの症状が強かったり、自傷したい衝動に駆られたりする場合も病院へ行くことをおすすめします。
逆に、気分の落ち込みがあっても短時間であったり、子育て以外の時間を楽しめ、子育ても問題なく行えたりしているようであれば、子育て鬱の可能性は低いでしょう。
子育て鬱が子どもに与える影響
子どもは親の気持ちに敏感です。親の気持ちが不安定だと、子どもも情緒不安定になったり、成長過程で何らかの問題が出てきたりする懸念があります。
つらさを感じていても、子どものためにと無理をして頑張りすぎてしまい、結果子育て鬱になってしまったら本末転倒です。母親がストレスや子育てに関する重圧を背負って子育てすることで、子どもの心身への影響があるとも言われています。
子どもの健やかな発育のためにも、まず親自身が無理をせずに、周囲に相談をしたり適切なサポートを受けたりすることが大切です。(具体的なサポートについては後述します)
なぜ子育て期に鬱病になってしまうのか?
子育て期に鬱病になってしまう原因としては様々なものが考えられます。多くの要因が絡みあって育児への不安を抱え、場合によっては育児ノイローゼになることも。さらに悪化すると子育て鬱になる可能性もあるでしょう。
ここからは、子育て時に鬱病になってしまう理由をひとつひとつ解説していきます。
子育て時に鬱病になる理由1.睡眠不足と疲労
子どもが頻繁に夜泣きをする場合、夜の睡眠時間を確保することが難しくなります。日中も産後しばらくは2~3時間ごとに授乳が必要だったり、子どもの面倒を見なければならなかったりと、昼寝をする時間を確保するのも至難の業です。
仕事をしている人は昼も夜も眠れないことが多くなります。結果、慢性的な睡眠不足に陥り、疲労が蓄積していきます。
また子育てが思い通りにいかない、子供中心の生活で自分の時間がないなどにより、閉塞感や孤立感を感じやすくなり、疲労に繋がります。
子育て時に鬱病になる理由2.育児への不安と過度なプレッシャー
助産師や保育士、大家族など一部の方を除いて、多くの人は子育てを習ったり経験したりすることはほとんどありません。母親は、育児書やSNSなどで情報収集しながら子育てをすることが多いでしょう。
現代はインターネットの発達もあって、多くの情報に触れています。しかし、それがあだとなり「育児書や専門家の言う通りにしなければ」とプレッシャーになってしまうことも。
ただでさえ、初めての子育ては慣れないことだらけで不安を感じやすいものです。慣れない子育てへの不安と、完璧であろうとする過度のプレッシャーが、子育て鬱のきっかけになってしまうこともあります。
子育て時に鬱病になる理由3.周囲からのサポート不足
父親の仕事の帰りが遅かったり、頼れる家族・友人・知人が周囲にいなかったりなどで周囲からの協力が得られにくい場合、母親のワンオペ育児になってしまうことも多いでしょう。
困ったときに周囲に相談したり頼ったりできる相手がいないことで、母親1人に負担が重くのしかかってきます。ワンオペ育児になると、自分の時間を確保することも難しくなって息抜きもできず、ますます疲労感や孤独感が増していきます。
子育て時に鬱病になる理由4.パートナーや家族との関係性
パートナーや家族との関係性も子育て鬱の発症に関わってくる場合があります。
例えば、夫が仕事ばかりで全く育児に協力してくれない、夫の子育てへの理解が乏しくコミュニケーションがうまく取れない、実の両親や義両親との関係性が良好でないなどの場合は、大きなストレスになります。
こういったパートナーや家族との関係性によるストレスが、子育て鬱の引き金となることもあります。
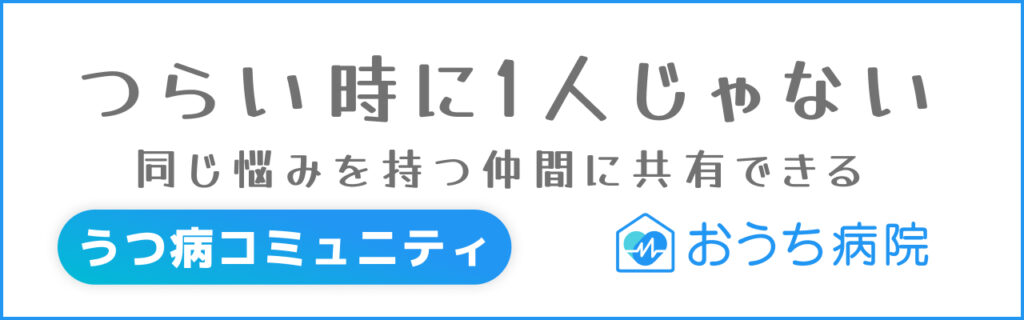
子育て時に鬱病になる理由5.産後のホルモンバランスの乱れ
産後鬱限定ではありますが、出産直後から授乳中までは、女性はホルモンバランスが乱れることによって鬱を発症する場合もあります。
女性の鬱病へのかかりやすさは男性の2倍であることが知られており、特に産褥期では鬱病にかかりやすいとされています。産後はエストロゲンという女性ホルモンが急激に下がるなど、女性特有のホルモンバランスの変化があり、エストロゲンの低下はしばしば鬱病を引き起こします。
【パートナーへ】子育て鬱の妻(夫)への具体的な接し方・サポート術
もしパートナーが子育て鬱になってしまった場合、どのように接していけばよいのでしょうか。
まず何よりも大切なのは、子育て鬱になったパートナーにゆっくりと休息を取ってもらう事です。そして、どちらかだけが子育てを担うのではなく、パートナーと二人で子育てをしていくという姿勢を示すことが重要です。
具体的には以下のようなことを心がけるとよいでしょう。
- 子育てでつらいことや大変に感じていることはないかたずね、不安を共有する
- 家事や育児を積極的に行う
- 役割分担をする
- ミルクも併用している場合、夜の授乳やおむつ替えを代わりに行う
- 「いつもありがとう」など日頃の感謝の気持ちを伝える
- 休日に子どもと一緒に公園に行くなどして、パートナーに1人で過ごす時間を持ってもらう
- 病院の受診が必要な状態であれば、付き添って病状をパートナーの代わりに医師に説明する
パートナーがどんなことを不安や負担に思っているのか、しっかりと共有して家事や育児を分担し、負担を軽減することが大切です。
また、子育て鬱にかかった本人は、病状を医師に説明することや受診の手続きなども精神的・体力的な負担になり得ます。病院受診が必要な状態であれば、受診に付き添って代わりに病状説明などをすることは、普段から一緒に過ごしているパートナーであるからこそできることです。
【ご両親へ】子育て鬱の娘(息子)への具体的な接し方・サポート術
自分の娘(息子)や義理の娘(息子)が子育て鬱になってしまった場合、両親だからこそできるサポートは以下のようなものがあります。
- 子育ての悩みや不安を本人が話しやすいように、いつでも話を聞ける態勢を整えていることを本人に伝える
- 子どもを預かり、子育てを休める時間を作ってあげる
- 家事を代わりに行う
- 「自分たちの頃はこうだった」など子育ての持論を押し付けない
ただし、両親や義両親との関係性によっては、良かれと思ってやったことが余計なお世話だと思われてしまい、かえってストレスになってしまうことも。
「家事だけをしてほしい」「代わりに子どもと遊んでほしい」など、人それぞれ両親や義両親に求めることは異なります。しっかりとコミュニケーションを取り、患者本人が望むサポートをしていくことが大切です。
また、話をいつでも聞く態勢を整えていることを、普段から伝えておくことは、とても重要なことです。周囲に頼っていいのだという安心感を与えることに繋がります。
家族だけで抱え込まないで!子育て支援サービスや制度を活用しよう
子育て鬱になってしまったら、治療と並行して、子育ての負担を軽減していきたいところ。
患者本人や支える家族が無理をして潰れてしまわないように、子育てをサポートする専門機関や公的サービスを上手に活用していきましょう。
子育ての相談機関や公的サービスを利用する
未就学児の子育てに関する困りごとなどは、子育て支援センターや保健所などで相談することができます。各市町村が運営していますので、近隣の施設を検索してみましょう。
各市町村の役所でも子育て相談に関する窓口がある場合があるため、お住まいの市町村の公式ホームページをチェックしてみることをおすすめします。
産後鬱の場合は、出産した医療機関や助産院でケアを受けられる場合もあります。
休養のために医療機関や助産院に宿泊できたり、助産師などが自宅訪問してケアしてくれたりなどさまざまなタイプがあり、ご自身の状態にあわせて利用を検討してみましょう。
また、就学児の子育てに関する悩み事などは児童相談所にて相談することができます。
同年代の親同士等のコミュニティに参加する
子育て支援センターや保健所では、同年代の子どもを育てている親同士の交流の場を設けている場合があります。同じ子育て世代の親同士が情報交換などをすることで繋がりができ、孤独感を和らげることに繋がります。
親子で参加できるイベントなどの情報も得ることができるため、こうしたイベントを活用することで、同年代の子どもを育てる親同士で交流しやすくなるでしょう。
また、職員にざっくばらんに相談ができて、悩み事を1人で抱え込まずに済み、かなり気が楽になることも。
核家族化が進み、地域の繋がりも希薄になっている昨今、こうした親同士の繋がりや気軽に相談できる場所へ行くことは、子育ての不安感や負担感の軽減に繋がります。
育児・家事をサポートしてもらえる制度・サービスを利用する
一時的にでも育児と家事から離れる時間を作って休む、または負担を軽減するために、一時預かりやファミリーサポート、家事代行サービスやベビーシッターなどの利用も検討しましょう。
一時預かりをしてくれる施設は主に保育所や幼稚園などです。各市町村が主体となって事業を運営しており、対象児童の条件はそれぞれの施設ごとに異なっています。お住まいの地域の一時預かり施設については「一時保育 地域名」で検索してみましょう。
ファミリーサポートとは、育児に援助が必要な人と育児を援助できる人とをマッチングさせるサービスです。各市町村が主体となって運営しています。乳幼児から小学6年生まで利用することができます。
自治体によっては産後ケアが充実しており、産後すぐであればサービスを利用して家事や育児の負担を軽減することも可能です。
参照元:令和7年度放課後児童対策・こども・子育て支援関連予算概算要求の概要|こども家庭庁
子育て鬱と感じたら患者自身ができるセルフケア
ここまで、他人を上手に頼って家事や育児の負担を軽減することや、心配事を家族だけで抱え込まないことの大切さについて解説してきました。ここからは、他人を頼ることとあわせて実施したい、患者自身ができるセルフケアについて解説していきます。
「子育て鬱かもしれない」と感じたときに、大切なのは休養・運動・栄養の三つです。
休養に関してはこれまでに解説してきましたが、あわせて自分がリラックスできることをしたり、リフレッシュできることをしたりすることも効果的です。
例えば、マッサージを受ける、趣味の活動をするなど。疲れない範囲で、自分が「楽しい」と感じることをするとよいでしょう。
適度な運動は、体力がつき、気分を向上させることが期待できます。激しい運動でなくとも、外に出て散歩をする、ラジオ体操をするなどの簡単な運動から始めると、運動へのハードルが下がります。
また子育て鬱の予防として、6~8時間の睡眠がよいとされています。適度に体を動かすことは、質のよい睡眠にも繋がります。
栄養に関しては、3食しっかりと食べることと、過度な飲酒を避けることが重要となってきます。飲酒をすると睡眠が浅くなり、子育て鬱の悪化に繋がる恐れもあるため、飲酒する場合は1杯程度に留めておきましょう。
子育て鬱の回復をサポートしてくれる栄養素もあり、積極的にとっていきたいところ。日々の食事とあわせて、必要に応じてサプリメントを上手に利用することも患者自身ができるセルフケアの一つです。
参照元:うつ病の認知療法・認知行動療法|厚生労働省 こころの健康科学研究事業
子育て鬱の回復をサポートする「栄養」の力
心の元気を取り戻すために、症状改善をサポートしてくれる栄養をとることは大切なことです。ここからは、それぞれの栄養素の期待される効果とおすすめの食品を解説していきます。
食欲がない場合や栄養素を意識するのが負担に感じる場合は、医師に相談のうえ医療用サプリメントを処方してもらう方法もおすすめです。
幸せホルモン「セロトニン」の材料となるトリプトファン
「幸せホルモン」として知られ、脳内の神経伝達物質の一つであるセロトニンは、精神の安定に作用します。セロトニンが減少すると、子育て鬱に限らず、鬱病にかかりやすいとされています。セロトニンを作るには、材料となるトリプトファンという必須アミノ酸をとる必要があります。
多く含まれる食品
チーズや牛乳などの乳製品、鶏卵、大豆などの豆類、鶏むね肉、レバーなど
セロトニンの生成を助けるビタミンB群
トリプトファンからセロトニンが作られる際、特にビタミンB6が必要になります。
トリプトファンとビタミンB6を一緒にとることで、抑うつ症状の改善に繋がったという研究も報告されており、トリプトファンを多く含む食材をとる時にはビタミンB6を多く含む食品を一緒にとることを意識すると、より効果が期待できます。
多く含まれる食品
レバーなどの肉類、まぐろやカツオなどの魚介類、にんにくやパセリ、ドライトマト、ブロッコリーなど
脳と神経の健康をサポートするオメガ3脂肪酸
オメガ3脂肪酸(主にDHA・EPA)は、神経伝達をスムーズにして、脳と神経の健康をサポートします。抗炎症作用や認知・情動などの脳機能を安定化させる働きがあるとされています。
これにより、オメガ3脂肪酸は不安を軽減したり、抑鬱症状を緩和したりといった効果が期待されており、研究が進んでいます。
多く含まれる食品
サバ・イワシ・サンマ・アジ・マグロ・サケ・カキなどの魚介類、えごま油、亜麻仁油など
気分や認知機能を支えるビタミンD
カルシウムの吸収を助け、骨の生成に関わることで知られるビタミンDには抗炎症・抗酸化作用もあります。さらに神経伝達物質の生成やホルモンの調節にも関係しており、気分の安定や認知機能を支えています。
ビタミンDは日光を浴びることで、体内で生成されますが、食品からも摂ることができます。
多く含まれる食品
キクラゲ、干ししいたけ、しらす干し・サケ・マグロ・イワシ・サンマなどの魚介類、鶏卵など
ストレス対抗力を高めるビタミンC
体の中で、ストレスに対抗するホルモンを生成する際にビタミンCが使われます。
ビタミンCによりストレスが軽減されるという研究結果も報告されていて、ストレスとビタミンCの関係性は非常に深いと言えます。
多く含まれる食品
アセロラやゆずなどの果物類、ピーマンやブロッコリーなどの野菜類、豚肉など
※ビタミンCは熱に弱い性質を持っているため、効率よくとるには果物や野菜類は生で食べるようにするとよいでしょう。加熱する際は、ゆでるよりも蒸す調理方法が、ビタミンCの損失は少なく済みます
リラックス効果をもたらすミネラル
マグネシウムは神経の興奮を抑えたり、不安やストレスの軽減に働いたり、リラックス作用をもたらします。
亜鉛はビタミンDと同様にセロトニンの生成や抗炎症・抗酸化にも関わり、欠乏すると鬱状態に繋がる可能性があります。
子育て鬱の回復をサポートするために、マグネシウムや亜鉛などのミネラルをしっかりととるようにしましょう。
多く含まれる食品
| 栄養素 | おすすめの食品 |
| マグネシウム | ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ)、ほうれん草、海藻類、豆類、玄米など |
| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、豚肉、卵黄、チーズなど |
ご家族がつぶれないためには、鬱病患者の家族をサポートするコミュニティの活用がおすすめ
子育て鬱は患者本人がつらいのはもちろんですが、サポートする家族も悩みを抱え込んでしまうと、心身ともに疲弊して共倒れしてしまう危険性もあります。子育て鬱をサポートする家族も、1人で悩みを抱え込まずに、同じ悩みを持った人たちと励ましあったり、相談しあったりできる環境が必要です。
鬱病のコミュニティであるオンライン疾患コミュニティでは、同じ悩みを持った人たちと繋がり、子育て鬱のケアに関する情報交換をすることもできます。子育て鬱に関する相談ができ、専門家にアドバイスや意見をもらうこともできます。
オンライン疾患コミュニティに参加できるのは登録した人のみなので、安心して利用できます。
登録は無料ででき、登録後はすぐに利用開始できますので、少しでも気になる方はぜひ気軽に登録して参加してみてください。
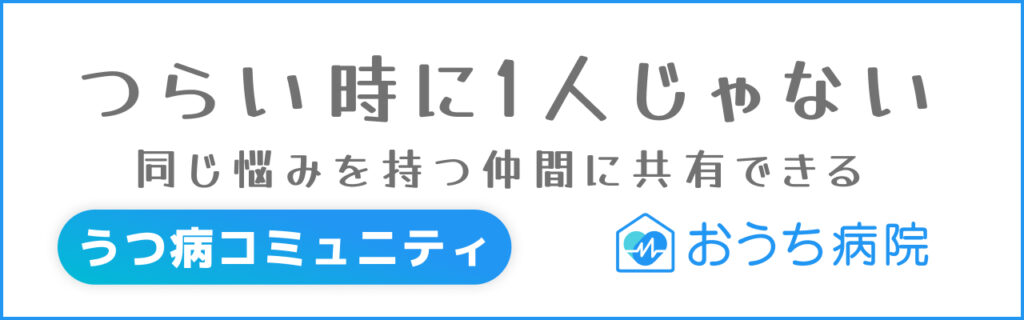
子育て鬱の家族を支える時こそ、同じ悩みを抱える仲間と情報交換しよう
家族が「子育て鬱なのでは?」と感じた時や子育て鬱の家族を支える時、「理解してもらえないのでは?」といった思いや恥ずかしさなどで、なかなか周囲に相談できず、悩んでしまう方は多いです。
子育て鬱の患者本人がつらいのはもちろんですが、支える側の家族も病気になってしまったり、離婚に至ってしまったりするケースもあります。
そんなつらい思いをしないためにも、悩みを1人で抱え込まずに誰かに話してみてはいかがでしょうか。
本人も家族もつらい思いをしてしまう子育て鬱。
家族が「子育て鬱かも?」と思った時は、1人で悩まずに、ぜひオンライン疾患コミュニティをご活用ください。