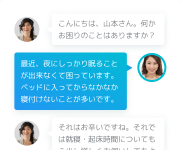ニキビを発症した場合、ニキビに効くと思われる市販薬を症状を考慮せずに使用してしまったというケースは多いでしょう。しかし、痛みや熱を伴ったり化膿したりしている場合には、皮膚科を受診することでより効果的な処方薬をもらえます。
では、一般的にどのような薬がニキビにおすすめと考えられているのでしょうか。
本記事では、ニキビに効果的な11種類の薬について、症状や原因とともに解説します。
この記事で分かること
- ニキビは進行段階や重症度によって「白ニキビ」など6種類に分けられ、それぞれ治療法が異なる
- 軽症の場合はスキンケアやターンオーバーを整える成分、重症の場合は抗菌・抗炎症作用の強い成分が必要
- ニキビの処方薬には過酸化ベンゾイルやディフェリンゲルなどの塗り薬と、ミノマイシンなどの飲み薬がある
「今すぐニキビを改善したい」「ニキビに適切な治療薬が欲しい」という方は「おうち病院 オンライン診療」を利用してみましょう。
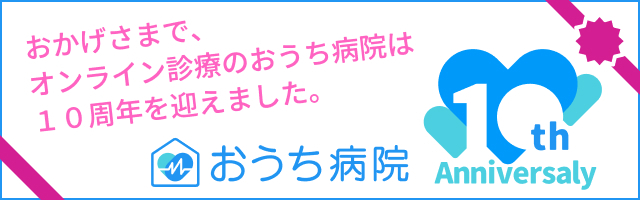
目次
ニキビの症状と原因
ニキビは、皮脂や死んだ皮膚細胞、アクネ菌により皮膚の毛穴が詰まって発生する皮膚症状です。進行段階ごとに「白ニキビ」や「赤ニキビ」といった呼称があります。
自分のニキビがどのタイプに該当するかを見分けることが重要です。細かい種類についてみていきましょう。
マイクロコメド(微小面皰)
マイクロコメド(微小面皰)は、毛穴の詰まりが肌全体にポツポツと発生している状態です。進行するとニキビになります。
皮脂や垢などにより発生するものの、見た目は平常と変わりません。なお、洗顔料や化粧品が十分に洗い流されておらず、肌に残ることも原因となります。
白ニキビ(閉鎖面皰)
白ニキビは、毛穴に透明な皮脂がたまってできる白いできものです。毛穴の先端にたまった皮脂が、白く小さな点のように見えます。角栓のようにも見えるものの、毛穴が完全に閉塞されているかどうかで見分けることができます。
黒ニキビ(開放面皰)
黒ニキビは白ニキビが進行し、毛穴の開口部が酸化して黒色になった状態です。紫外線や強い洗顔によるダメージが主な原因となります。また、白ニキビと併せて「コメド(面皰)」と呼ばれる場合もあります。
赤ニキビ(赤色丘疹)
白ニキビや黒ニキビにアクネ菌が侵入し、肌が細菌の増殖を抑えようとして炎症を起こしている状態です。炎症の原因は主にアクネ菌によるものの、アクネ菌や紫外線によっても引き起こされます。また、痛みやかゆみなどを感じるケースもあります。
黄ニキビ(膿疱)
黄ニキビ(膿疱)はアクネ菌に加え黄色ブドウ球菌が侵入し、痛みやかゆみ、化膿を伴う状態です。呼称の通りニキビの中央が黄色く見えるほか、炎症を起こして周囲が赤く腫れているという特徴があります。
紫ニキビ(嚢腫)
赤ニキビが悪化して血膿がたまった状態になり、重度の腫れと痛みを伴うニキビです。日常的なニキビケアや保険適用の治療では根本治療が難しく、保険適用外の治療と薬が必要になります。ホルモンバランスの乱れや血行不良などが原因です。
ニキビの塗り薬の選び方
ニキビの塗り薬は、ニキビの症状に適したものを選ぶ事が重要です。
ニキビは、「白ニキビ→黒ニキビ→赤ニキビ→黄ニキビ・紫ニキビ」の順に悪化していきます。
ニキビの軽症、中等症、重症の定義は以下の通りです。
| 症状の重さ | 片顔の炎症性皮疹(ニキビ)の数 |
|---|---|
| 軽症 | 5 個以下 |
| 中等症 | 6 個以上 20 個以下 |
| 重症 | 21 個以上 50 個以下 |
| 最重度 | 51 個以上 |
軽症の場合
軽症の場合は、まだ白ニキビ・黒ニキビの症状です。
白ニキビや黒ニキビの段階では、まだアクネ菌が侵入しておらず、肌の炎症も起きていません。そのため、アクネ菌に対する抗菌までは不要です。
この初期段階でケアする事ができれば、悪化をおさえ、回復も早いでしょう。この段階でのケアは、スキンケアを中心にアプローチします。肌の調子を整える成分が含まれた塗り薬を選びましょう。
ニキビは、皮脂と古い角質が混ざり合って毛穴に詰まる「角栓」が引き金となります。そのため、ターンオーバーを整えてくれるものを選びます。
古い角質を取り除いて毛穴の詰まりを解消する働きのあるサリチル酸製剤、肌のターンオーバーの活性化を促すユベラなどがおすすめです。
中等症の場合
中等度の場合は、白ニキビや黒ニキビが赤ニキビの症状へと進行しています。
白ニキビや黒ニキビにアクネ菌が侵入して、肌が炎症を起こしている状態です。この状態の時は、アクネ菌の増殖を抑え肌の炎症に作用する塗り薬を選びます。
実は、白ニキビや黒ニキビの場合は市販薬でも効果を感じられるますが、赤ニキビになると、市販薬では効果を感じにくくなるので、処方薬をおすすめします。
洗顔後に使用することでアクネ菌の増殖を抑制し、炎症を鎮める作用のあるダラシンT、皮膚の角化を正常化して毛穴の詰まりを解消し、抗菌作用によりアクネ菌の増殖も抑制する、アズノール軟膏がおすすめです。
重症の場合
重症の場合は、黄ニキビ・紫ニキビへと進行しています。この場合、重度の痛みや腫れ、かゆみ、化膿などの症状が表れています。
黄ニキビは、アクネ菌に加えて黄色ブドウ球菌が侵入、紫ニキビは赤ニキビの悪化です。
この場合は、まずは炎症を静め根本的にニキビ治療を進める必要があります。
アクネ菌やブドウ球菌に対する抗菌作用のあるゼビアックス、殺菌効果のある過酸化ベンゾイルと毛穴詰まりの改善に働きかけるアダパレンの2種を配合した塗り薬などがおすすめです。
過酸化ベンゾイル/アダパレン配合ゲルは、膿を伴う重症ケースに多く用いられます。
ニキビの飲み薬の選び方
ニキビ薬の飲み薬を選ぶ際は、塗り薬同様ニキビの症状の進行に応じた薬を選ぶ必要があります。
軽症、中等症、重症、最重度により、治療のアプローチが異なります。そのため、自身のニキビの重症度やニキビの症状を把握する必要があります。
ニキビの症状は、「白ニキビ→黒ニキビ→赤ニキビ→黄ニキビ・紫ニキビ」の順に悪化していきます。
スキンケアや塗り薬だけでなく、飲み薬を検討している方は、本当にご自身のニキビの症状や進行度に合っているのかどうかご確認ください。または皮膚科の医師に相談しましょう。
症状別の飲み薬を選ぶポイントを、以下で解説しています。
軽症の場合
軽症の場合は、まだ白ニキビ・黒ニキビの症状です。アクネ菌は侵入しておらず、肌の炎症まで進行していません。そのため、アクネ菌に対する抗菌までは不要です。
この初期段階で洗顔や洗顔後のケアなどを中心にしっかりケアする事で、悪化をおさえます。
多くの場合は、この段階では皮脂や角質ケアを行い毛穴がつまる状態を防ぐ、洗顔後に適切な塗り薬を行う等で対処しますが、肌の調子を整える薬も良いでしょう。
色素沈着に対して効果・効能が期待できるシナール、肌のターンオーバーの活性化に働きかけ、肌トラブル全般に対して有効なユベラなどがおすすめです。
中等症の場合
中等度の場合は、白ニキビや黒ニキビが赤ニキビの症状へと進行しています。
アクネ菌が侵入して肌が炎症を起こしている状態ですので、アクネ菌の増殖を抑え、肌の炎症を静めなければなりません。
そのため、アクネ菌に作用する飲み薬、殺菌作用のある飲み薬、肌のターンオーバーに働きかける飲み薬等が推奨されます。
中等症の場合、市販薬では大きな効果は期待できませんので、処方薬が推奨されます。
ニキビによる色素沈着や肌の赤みを改善するトランサミン、細菌の増殖を抑え、炎症を鎮める抗生物質、ビブラマイシン、ロキシスロマイシンなどがおすすめです。
重症の場合
重症の場合は、黄ニキビ・紫ニキビへと進行しています。この場合、重度の痛みや腫れ、かゆみ、化膿などの症状が表れています。
黄ニキビは、アクネ菌に加えて黄色ブドウ球菌が侵入、紫ニキビは赤ニキビの悪化です。
この場合は、まずは炎症を静め根本的にニキビ治療を進める必要があります。
ニキビの原因となる細菌の増殖を抑制するほか、抗炎症作用や皮脂分泌抑制作用のあるミノマイシン、化膿を伴う重度のニキビや炎症性のニキビや抗生物質が効かないニキビに対して効果的なイソトレチノインがおすすめです。
イソトレチノインは保険適用外となり自由診療にあたります。
ニキビには塗り薬と飲み薬がある
ニキビ治療薬は、塗り薬と飲み薬の2種類に分類されます。市販でも入手できるものから、医師の処方が必須となるものまで多種多様です。
ここでは、代表的な11種類のニキビ治療薬を解説します。薬を選択・使用する際の参考にしてみましょう。
| 名称 | 対象のニキビ | 使用頻度 | 市販/処方薬 |
| 過酸化ベンゾイル | ニキビ全般 | 1日1回 | 処方薬 |
| 過酸化ベンゾイル/アダパレン配合ゲル | 重度(赤~黄ニキビ) | 1日1回、夕方~就寝前 | 処方薬 |
| ディフェリンゲル | 軽度から中等度(白~赤ニキビ) | 1日1回、就寝前 | 処方薬 |
| ミノマイシン | 重度(赤~黄ニキビ) | 1日1~2錠(12時間または24時間あける) | 処方薬 |
| ゼビアックス | 軽度(白~黒ニキビ) | 1日1回、最大4週間 | 処方薬 |
| デュアック配合ゲル | 重度(赤~黄ニキビ) | 1日1回 | 処方薬 |
| ビブラマイシン、ミノマイシン、ロキシスロマイシン | 重度(赤~黄ニキビ) | 1日1回 | 処方薬 |
| トランサミン | 重度(赤~黄ニキビ) | 1日2回 | 処方薬・市販薬どちらもある |
| シナール | 軽度から中等度(白~赤ニキビ) | 1日1回 | 処方薬・市販薬どちらもある |
| ユベラ | 軽度から中等度(白~赤ニキビ) | 1日1回 | 処方薬・市販薬どちらもある |
| イソトレチノイン | 重度(赤~黄ニキビ) | 1日1~2回、食後 | 処方薬 |
| ダラシンT | 重度(赤~黄ニキビ) | 1日2回 | 処方薬 |
| サリチル酸製剤 | 軽度から中等度(白~赤ニキビ) | 1日2回 | 処方薬・市販薬どちらもある |
| アズノール軟膏 | 軽度から中等度(白~赤ニキビ) | 1日数回 | 処方薬 |
これらのいずれかのニキビ治療薬を処方してほしい方は、まずは医師にご相談ください。
ニキビに効くおすすめの塗り薬
それでは、ニキビに効くとされるおすすめの塗り薬について、詳しく解説いたします。日々のケアの参考にしてみてください。
紹介する薬の中には、市販薬でも手に入るものと、処方箋でしか手に入らないものがあります。
過酸化ベンゾイル、アズノール軟膏、ディフェリンゲル、ダラシンT、ゼビアックス、過酸化ベンゾイル/アダパレン配合ゲル、デュアック配合ゲルは、医療機関を受診して処方されます。
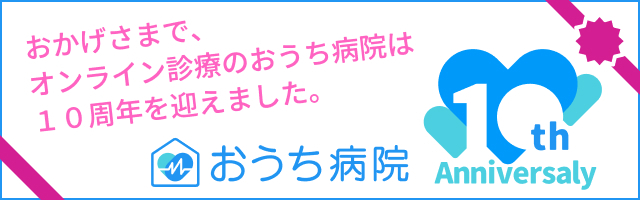
ここからは、それぞれのニキビ治療薬について解説します。
塗り薬1.過酸化ベンゾイル
過酸化ベンゾイルは、白~黄色の一般的なニキビに効果的な成分です。市販薬として手軽に購入でき、ニキビケアに広く用いられています。皮脂の分泌を抑え、毛穴の詰まりを解消するとともにニキビの原因となる細菌の繁殖を防ぎ、炎症を抑える効果もあります。
使用頻度は1日1〜2回が推奨されており、症状に応じて塗布量や使用頻度は調整可能です。副作用としては、使用を開始してしばらく肌の乾燥やかゆみ、赤みが出る場合があるものの、使用を続けることで徐々に症状が改善される傾向にあります。
塗り薬2.サリチル酸製剤
サリチル酸製剤は、ニキビ治療において広く使用されている局所適用薬です。皮膚の角質層を柔らかくし、古い角質を取り除いて毛穴の詰まりを解消する働きがあります。
ニキビの発症を防止・改善する効果があるため、主に軽度から中等度のニキビに対して処方される薬です。ジェルやクリーム、ローションなどの形で調剤されており、ニキビができやすい部位に1日1〜2回塗布します。
また、サリチル酸を配合した市販医薬品として「10%サリチル酸ワセリン軟膏」があります。長期間の使用および一度に過剰使用した場合、皮膚が乾燥したり刺激を受けたりする可能性があるため、用法・用量を守って使用しましょう。
塗り薬3.アズノール軟膏
アズノール軟膏は、カモミールから抽出された「アズレン」を主成分とする薬です。特に、軽度から中等度のニキビ治療に効果があります。細菌に対する効果はないものの、肌に優しい成分のため、乳児からお年寄りの方まで幅広く処方されています。
アズレンは皮膚の角化を正常化して毛穴の詰まりを解消するため、ニキビの予防に効果的です。また、抗菌作用により、ニキビの原因となるアクネ菌の増殖も抑制します。
アズノール軟膏の使用方法は、1日数回、清潔な肌に薄く塗布するのが一般的です。ニキビの状態や数によっては使用回数や量が異なる場合があるため、医師の指示に従って使用しましょう。
塗り薬4.ユベラ
ユベラはニキビ痕の改善効果が期待できる治療薬です。肌のターンオーバーが活性化されることで色素の排出が促され、色素沈着したニキビ痕が薄くなる可能性があります。シミや肝斑、そばかすの改善も見込めるため、肌トラブル全般に対して有効です。
また、ユベラに含まれるビタミンEは抗酸化作用があり、肌の老化防止にも役立つ成分です。そのため、ニキビ治療だけでなく、美肌を追求する患者にも処方されます。ただし、ビタミンEは脂溶性ビタミンのため、医師の指示に従い用法・用量を守って服用しましょう。
なお、ユベラは軟膏タイプだけでなく、錠剤タイプもあります。ニキビ痕の治療には主に錠剤タイプが選択されるものの、医師の判断により異なります。
塗り薬5.ディフェリンゲル
ディフェリンゲルは、処方箋薬として用いられるニキビ治療薬です。主成分であるアダパレンはレチノイド系の成分であり、皮膚のターンオーバーを促進する効果があります。特に、黒ずみや炎症を伴うニキビ(黒ニキビ〜黄ニキビ)に効果的です。
一般的な用法・用量としては、1日1回適量を塗布します。副作用として肌の乾燥やかゆみなどが起こる可能性がありますが、多くの場合は継続使用により徐々に症状が改善します。しかし、副作用が強い場合や症状がなかなか改善しない場合は、医師に相談しましょう。
塗り薬6.ダラシンT
ダラシンTは、デュアック配合ゲルにも含まれるクリンダマイシンを主成分とした抗生物質です。ニキビの原因となるアクネ菌の増殖を抑制し、炎症を鎮める作用があります。中等度から重度のニキビに効果的です。
軟膏やゲル、ローションなどの形で調剤されており、1日2回の頻度で洗顔後に使用します。4週間以上使用すると耐性菌が出現するおそれがあるため、再診の際には注意が必要です。また、一般的な副作用としては皮膚のかゆみや発疹、乾燥が挙げられます。
塗り薬7.ゼビアックス
ゼビアックスは、主に口唇ヘルペスや帯状疱疹などのウイルス性皮膚疾患に対して効果的な抗ウイルス薬です。さらに、アクネ菌やブドウ球菌に対する抗菌作用も持ち合わせているため、ニキビ治療にも用いられています。
有効成分であるオゼノキサシンはウイルスのDNA合成を阻害し、細菌の増殖を抑え、感染の広がりを防ぐことが可能です。重度のニキビに効果があり、他のニキビ治療薬と併用されるケースが多い傾向にあります。
使用方法としては1日数回、患部に適量を塗布します。長期にわたって使用した場合、細菌が抗菌耐性を持つ可能性があるため、最大4週間以上の継続はできません。また、使用中の副作用として一時的に皮膚のかゆみや赤み、刺激感が感じられる場合があります。
塗り薬8.過酸化ベンゾイル/アダパレン配合ゲル
殺菌効果のある過酸化ベンゾイル、毛穴詰まりの改善に働きかけるアダパレンの2種を配合した外用薬です。過酸化ベンゾイル単体では効果が感じられないケースや膿を伴う重症ケースなどに処方されます。
皮脂分泌の抑制作用がある過酸化ベンゾイルに加え、アダパレンが皮膚のターンオーバーを促進します。古い角質を剥がして新しい皮膚細胞へと入れ替える作用があるため、黄ニキビの治療にも効果的です。
使用頻度としては1日1回の使用が推奨されており、症状に応じて医師の指示に従って使用します。また、副作用として乾燥やかゆみ、赤みが起こる場合があります。比較的強力な薬のため、医師の診断が必要です。
塗り薬9.デュアック配合ゲル
デュアック配合ゲルはニキビ治療に用いられる外用薬です。過酸化ベンゾイルに加え、クリンダマイシンという2種類の有効成分を配合しています。クリンダマイシンは抗生物質であり、ニキビの原因となる細菌の増殖を抑え、炎症を鎮める効果があります。
軽度から中等度の炎症を伴うニキビに効果的で、1日1回の使用が推奨されています。適切な量を塗布し、医師の指示に従って使用することが大切です。ニキビの状態によっては、他のニキビ治療薬と併用される場合があります。
なお、デュアック配合ゲルは市販されておらず、医師の処方箋が必要な薬です。副作用として一時的な皮膚のかゆみ・乾燥・赤み・刺激感がみられる可能性があります。
ニキビに効くおすすめの飲み薬
続いて、ニキビに効くとされるおすすめの飲み薬について、詳しく解説いたします。ニキビケアに飲み薬を検討している方は、参考にしてください。
ミノマイシン、ビブラマイシン、ロキシスロマイシン、イソトレチノインは医療機関を受診して処方されます。
なお、イソトレチノインは保険適用外となり、自由診療となります。
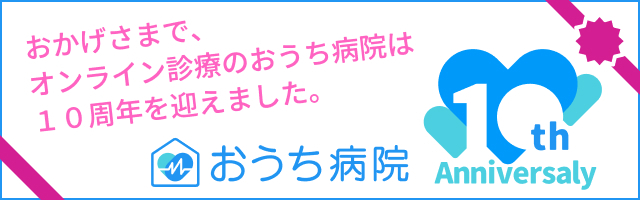
飲み薬1.ミノマイシン
ミノマイシンはニキビ治療に用いられる内服薬の抗生物質であり、中等度から重度のニキビに対して効果的です。ニキビの原因となる細菌の増殖を抑制するほか、抗炎症作用や皮脂分泌抑制作用もあり、ニキビの予防・改善に役立ちます。
薬の形状は一般的に、錠剤またはカプセルで処方されます。推奨される服用頻度は1日1〜2錠程度です。用量や治療期間については、ニキビの量や状態に応じて調整が必要となるため、必ず医師の指示に従いましょう。
ミノマイシンは抗生物質のため胃腸の不快感や吐き気、下痢などの副作用が起こる可能性があります。そのため、胃腸薬や整腸剤と併せて処方されるのが一般的です。
紫外線の刺激に弱くなる副作用もあるため、服用中は十分な紫外線対策を行なう必要があります。
飲み薬2.ビブラマイシン、ロキシスロマイシン
ビブラマイシン、ロキシスロマイシンはどちらもニキビ治療に使用される抗生物質です。ニキビの原因となる細菌の増殖を抑え、炎症を鎮める効果があります。細かな違いをみていきましょう。
ビブラマイシン
テトラサイクリン系の抗生物質です。ニキビの原因となるプロピオニバクテリウム・アクネ菌の増殖を抑える効果があります。通常、医師の指示に従って1日2〜4回、食後に服用します。
ロキシスロマイシン
マクロライド系の抗生物質です。ビブラマイシンと同様、プロピオニバクテリウム・アクネ菌をはじめとする細菌の増殖を抑える効果があります。テトラサイクリン系抗生物質に対してアレルギー反応があるケースや他の薬との併用が難しい場合に処方されます。
通常は1日2回、食後に服用します。抗生物質を服用する際は、自己判断で服用を中止するのは避けましょう。
飲み薬3.トランサミン
トランサミンは「トラネキサム酸」を主成分とし、ニキビによる色素沈着や肌の赤みを改善するために使用される薬です。メラニン色素の生成を抑制し、皮膚の色素沈着を防ぐ効果があります。また、抗炎症作用もあり、ニキビの炎症を鎮める働きも期待できます。
しかし、ニキビそのものを治療する薬ではなく、主に色素沈着や赤みの改善を目的とした薬です。そのため、一般的には他のニキビ治療薬と併せて処方されます。
トランサミンは医師の診断が必要な薬です。通常の服用方法としては、1日2〜3回食後に服用します。副作用としては、まれに胃腸の不快感や吐き気、食欲不振などを引き起こすケースが報告されています。
飲み薬4.シナール
シナールは炎症性ニキビによる色素沈着に対して効果・効能が期待できる治療薬です。一般的には1日1〜3回、1回1〜3錠を服用することが推奨されています。ただし、年齢や症状に応じて服用量の調整が必要です。
しかし、シナールを服用しても効果が現れない場合、長期間の連用は控えましょう。副作用として胃の不快感や悪心、嘔吐、下痢などが報告されているためです。仮に副作用が強く現れた場合は、速やかに医師の診断を受けましょう。
飲み薬5.イソトレチノイン
イソトレチノインは重症のニキビ治療に使用されている、海外製の強力な薬です。主に、化膿を伴う重度のニキビや炎症性のニキビ、抗生物質が効かないニキビに対して効果的です。ビタミンA誘導体によって皮脂腺の働きを抑制し、ニキビの発生を防ぎます。
また、イソトレチノインには角化細胞の分化を正常化する働きもあります。保険適用外の処方薬となるものの、ニキビの予防だけでなく、重度の炎症を鎮める効果も見込める治療薬です。
しかし、イソトレチノインは副作用が強く、日本国内ではまだ承認されていない治療薬です。服用の際、以下のような症状が現れる場合があるため、体調の変化に注意しましょう。
- 乾燥肌
- 皮膚の剥離
- 唇のひび割れ
- 頭痛
- 関節痛
飲み薬6.桂枝茯苓丸加薏苡仁(けいしぶくりょうがんかよくいにん)
桂枝茯苓丸加薏苡仁(けいしぶくりょうがんかよくいにん)は漢方薬の一種です。ニキビの根治に働きかける桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)、薏苡仁(よくいにん)の2種類を調剤しています。
2つの漢方薬が水分代謝や血行不良を改善し、皮膚の状態を整えるため、ニキビ予防やニキビ痕の治療に有効です。特に、ホルモンバランスの乱れやストレスが原因となる内因性のニキビに有効とされており、継続的な服用によって体質の改善も期待できます。
処方された際には通常、1日あたり7.5gを2〜3回に分け、経口にて服用を行ないます。また、西洋医学とは異なる治療アプローチをとるため、効果が現れるまでに時間がかかるケースが多いです。そのため、数週間から数ヶ月程度にわたる服用が推奨されます。
しかし、漢方薬は個人差があり、期待するような効果が出なかったり副作用が現れたりする場合もあります。漢方薬による副作用は極めてまれであるものの、胃腸の不快感や下痢などが報告されているため、万が一発生した場合は医師に相談しましょう。
まずは医師の診断からスタートする
ニキビ治療に取り組む場合は、かかりつけ医へ相談し、的確な診断を受けることを推奨します。ニキビの症状や原因には個人差があるだけでなく、他の重篤な皮膚症状と間違える可能性もあるためです。
自己判断で薬を選択・使用した場合、十分な効果が得られないだけでなく、症状が悪化したり、副作用が出たりする可能性もあります。しかし、医師の診断や指導があれば、適切に薬を使用したうえで治療に取り組むことが可能です。
また、病院またはクリニックにて相談することで、根本的な生活習慣やスキンケア方法などに関するアドバイスを得られます。病院やクリニックで得られた専門的なアドバイスであれば試しやすく、ニキビの根治につながるでしょう。
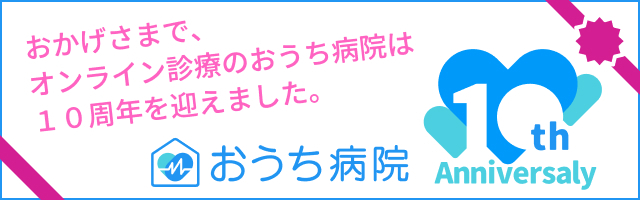
「おうち病院 オンライン診療」なら自宅でニキビ薬の処方が可能
「おうち病院 オンライン診療」は、インターネットを利用してニキビ治療の相談ができるサービスです。自宅などのリラックスできる場所にいながら、都合のよい時間帯に医師と相談することができます。
おうち病院なら、
✅ 初診から保険診療可能
✅ 通院時間や待ち時間が不要なので体調が悪い時でも安心受診
✅ スキマ時間で受診できるから、朝の準備中・会議の合間・夜のリラックスタイムにも◎
✅ 朝8時〜夜22時まで診察可能 平日夜間・土日祝日いつでも受診可能
✅ 予約時間どおりに診察開始だから、朝の準備中・仕事の合間・帰宅後にも受診可能。
✅ 処方せんは指定薬局へ自動送信 全国6,900店舗の薬局で受け取れるから便利
✅ 自宅配送サービス「おくすりおうち便」もあるので、薬局に行く時間がなくても安心
「おうち病院 オンライン診療」では、ビデオ通話やチャットを通じて医師とやりとりできます。悩んでいる症状や治療経過を詳しく伝えることで、通院と同様に適切なアドバイスや処方を受けることが可能です。また、ニキビに関する疑問や不安も解消できます。
また、『オンライン診療』を利用するメリットとして、通院の手間や待ち時間が省ける点が挙げられます。遠方に住んでいる場合や忙しい人でも手軽に受診できるため、ニキビの改善に役立つでしょう。
まとめ
一口にニキビといっても、進行状態や原因によりさまざまな種類が存在します。市販商品から薬を選択する際は、ニキビの種類や症状によって効果が異なる点に注意し、自分に適したものを選ぶとよいでしょう。
また、的確なニキビ治療を行なうために、まず皮膚科を受診することを推奨します。本記事で解説した種類の薬には、医師の処方箋がなければ入手できないものも存在するためです。医師の診断を受ける際に、ニキビ肌を根治するためのアドバイスも得られます。
おうち病院の『オンライン診療』は24時間365日オンラインチャットで対応しており、通院が困難な方でも簡単に利用できるサービスです。「自分のスケジュールに合わせてニキビの悩みを解消したい」という場合は利用を検討してみましょう。