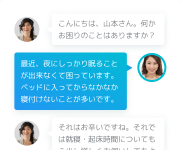オンライン診療が増えてきた昨今、「この皮膚トラブルはオンライン診療で大丈夫かな?」「対面で見てもらわないとダメかな?でも忙しいし」など、お悩みの方も多いと思います。
本記事では、具体的にオンライン診療可能な皮膚疾患について詳しく解説します。
思ったよりもオンラインで完結する皮膚科のトラブルは多いので、ぜひ参考にして賢く活用してください。

目次
オンライン診療の皮膚科を受診できる疾患例
オンライン診療が可能な皮膚疾患例と注意点や補足をお伝えします。
多汗症
体温調節に必要な量を超えて、過度に大量の汗が出る状態を、多汗症と言います。
特に、手、足、わき、頭、顔などに多く見られます。人によりますが、全身ではなく一部に大量の汗が出る局所多汗症の方が多く、症状の出る部位別に疾患名があります。
治療は、主に外用薬や内服薬、ボツリヌス療法などがあります。オンライン診療では、発汗の場所や程度、日常生活での困りごと等を詳しくヒアリングの上、適切な薬を処方します。
ただし、注射するボツリヌス療法や特殊な機械を用いるイオントフォレーシス療法等は、オンラインでは対応できません。
ヘルペス
単純ヘルペスウイルスによって引き起こされる感染症です。口唇(口唇ヘルペス)や性器(性器ヘルペス)に小さな水ぶくれの集まりができ、ピリピリとした痛みや痒みを伴います。一度感染すると、ウイルスは神経節に潜伏し、体の抵抗力が落ちた時などに再発を繰り返します。
すでに過去ヘルペスの診断を受けており再発症状を自覚している方や、頻繁に再発することに悩み、再発防止治療を検討する方には、特にオンラインが向いています。
症状に応じて、外用薬・抗ヘルペスウイルス薬・鎮痛剤を処方します。
ヘルペス再発時には、より早く抗ヘルペスウイルス薬を服用することが望まれるため、通院する時間がなかなかとれないよりは、すぐに受診できて処方してもらえるオンラインは心強い味方となるでしょう。
アトピー性皮膚炎
遺伝的要因やアレルギー体質などが原因で、皮膚のバリア機能が低下し、慢性の湿疹とかゆみが繰り返し現れる疾患です。
すでに治療を受けており、病状が安定している方の経過観察や薬の処方にはオンラインが適しています。症状が重く、対面での処置を必要と判断した場合は、対面治療をおすすめする可能性もあります。
アレルゲン(アレルギー反応を引き起こす原因となる物質)を調べるための検査として、以前は医療機関で血液検査をしなければなりませんでしたが、現代では検査キットを用いて自分で検査できる場合があります。
尋常性ざ瘡(ニキビ)
正式な病名を尋常性痤瘡(じんじょうせいざそう)というニキビは、毛穴に皮脂が詰まり、アクネ菌が増殖することで炎症を起こす疾患です。顔や背中、胸などにできます。
ニキビは、軽度から進行している症状によって、適切な処方薬も変わってきます。
オンライン診療においても、詳細に症状についてヒアリングし、場合によってはカメラ画像を用いて患部を確認して、適切な外用薬・内服薬を処方可能です。
ただし、重度のニキビで膿やしこりが広範囲にわたるなど、より詳細な診断が必要と判断した時、対面治療をおすすめする場合もあります。
脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)
皮脂の分泌が多い部分(頭皮、顔、胸、脇など)に発生する湿疹の一種で、フケや赤み、かゆみが生じる皮膚炎です。皮脂を好むマラセチア菌というカビの一種が原因とされています。
治療には、外用薬・内服薬のほか、使用するせっけんやシャンプーの指導が必要ですが、オンライン診療で可能です。特に、症状が安定していて継続治療の時は通院時間等を省くことができておすすめです。
その他、乾燥肌で冬などの痒みを感じる方や、軽度の皮膚炎の方もオンライン診療での対応可能です。

オンライン診療で皮膚科の受診が難しい疾患
思ったよりも多くの疾患でオンライン診療が可能な時代になりました。しかし、オンライン診療が難しい疾患もありますので、押さえておいてください。
医師や看護師の処置が必要な場合
火傷、切り傷、擦り傷などの外傷、皮膚がただれて膿が出ている、潰瘍(皮膚や粘膜が深く欠損した状態)や水疱が破れて悪化したなどの患部が重症な時などは、医師や看護師の直接的な処置が必要なため、オンライン診療では対応ができません。
また、乳幼児・小児(小学生~中学生まで)の皮膚症状、特に急な発疹、発熱を伴う場合、広範囲な場合などは、ウイルス感染症から来る発疹の可能性もあるため、対面診療をおすすめしています。
皮膚感染症
皮膚に関する感染症、例えば水虫などの真菌感染症や、とびひなどのウイルス感染症は、医療機関での詳細な検査が必要なため、対面診療をおすすめします。
ただし、診断をすでに受けており、経過観察と処方薬等の継続治療の場合、対応可能な場合もあります。
皮膚感染症には以下のような疾患があります。
- 水痘・帯状疱疹ウイルスによる水痘(みずぼうそう)
- 真菌性による白癬(はくせん)(水虫)
- ブドウ球菌によるとびひ
水虫やとびひは、タオル等の共有や銭湯、プール等で感染しやすく、原因を知ったうえでの適切な治療と行動が必要です。
蜂窩織炎(ほうかしきえん)
蜂窩織炎も、前述の細菌による感染症のひとつで、皮膚とその下の組織に症状が広がります。
傷口や虫刺されなどから細菌が侵入して発症することが多く、患部は赤く腫れ、痛みや熱感を伴い、悪寒・発熱・倦怠感・関節痛・頭痛が現れることもあります。原因菌は、主に黄色ブドウ球菌や化膿レンサ球菌です。
症状が重い場合は、原因菌を特定する検査や、抗生物質の静脈内注射・点滴が必要なこともあるため、オンライン診療では難しい病気と言えます。
皮膚腫瘍(ほくろ、粉瘤など)
良性または悪性の皮膚のできものです。
ほくろ(色素性母斑)や、皮膚の下に袋状のものができる粉瘤(ふんりゅう・アテローム)などがあります。皮膚がんの疑いがある場合の検査、良性か悪性かを判別するためには、ダーモスコピー検査(特殊な拡大鏡)など専門的な機器を使った詳細な観察や、組織検査が必要なため、オンライン診療では対応できません。
その他、医師が対面での詳細な診察が必要と判断した場合は、オンライン診療時でも対面診療をおすすめする可能性があります。
オンライン診療の皮膚科を賢く使う方法
ここまでで、皮膚科の治療は、オンライン診療と親和性が高い事にお気づきいただけたでしょうか。非常に広い範囲で、対応可能です。
画像を通してしっかり患部を見させていただくこともあります。
また、前述した初診は難しい疾患も、経過観察や同じ薬の処方など、継続治療の際には、オンライン診療を活用すると良いでしょう。多忙な時なども薬が切れる不安がなく、非常に便利です。
ただし、判断が難しい時、多忙で時間がとれない時など、ひとまずオンライン診療で相談してみるなど、オンライン皮膚科を賢く活用しましょう。
さくっと相談できて、対面検査が必要であれば案内してくれます。
オンライン診療の皮膚科を受診するメリット・デメリット
ここで、オンライン診療のメリットとデメリットをまとめました。確認して、自分にとってどちらが良いか参考にしてみてください。
オンライン診療皮膚科のメリット
皮膚科診療でオンラインを選ぶメリットは以下の通りです。
1.通院の手間がかからず時間も融通が利く
自宅や職場など、好きな場所から診察を受けられるため、クリニックへの移動時間や交通費がかかりません。これにより通院への手間と時間が削減できます。また、クリニックでの待ち時間が大幅に短縮されます。
Webで診療時間を予約するシステムですが、予約時間は早朝から深夜までまたは24時間受付しているところもあるため、スキマ時間を予約可能で、多忙で通院の時間がとれない方にとっては大きなメリットになります。
2.感染リスクの低減
皮膚科ですと、内科や発熱外来ほど心配はないとしても、やはりウイルス系感染症の患者さんがいないとも言い切れません。
オンラインであれば、クリニックの待合室など同質で他の患者さんと過ごす機会が無くなるため、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症リスクを避けられます。
3.プライバシーの確保
クリニックの待合室で他の患者さんと顔を合わせることなく、自宅などのプライベートな空間で診察を受けられます。「知り合いとばったり会ったら嫌だな」「見られたら恥ずかしい」などと心配する必要はありません。
デリケートな皮膚の悩みも相談しやすくなります。
4.治療の継続性の向上
通院のハードルが下がるため、慢性疾患(アトピー性皮膚炎や蕁麻疹・ヘルペスなど)の方が治療を中断することなく継続しやすくなります。
また、症状が現れる予兆の段階(ピリピリ・チクチク・むずむずなど)を察知したら、すぐに抗ヘルペスウイルス薬を飲むことが推奨されるヘルペスの方などには、非常におすすめです。通院がなかなか出来なくてもサクッとオンラインで受診し処方箋を受け取ることができるため、スムーズです。
5.地理的制約の解消
近くに皮膚科がない地域にお住まいの方や、皮膚科に通うまでの交通手段があまり便利ではない地域にお住まいの方でも、全国どこからでも専門医の診察をオンライン上で受けることが可能になります。
6.処方箋・薬の受け取りがスムーズ
自宅に薬を郵送してもらえるサービスを行っているオンラインクリニックもあります。
薬局に行かなくて済むのであれば、さらに手間と時間を短縮できるうえ、他の患者さんとの接触も完全にありません。

オンライン診療皮膚科のデメリット
オンライン皮膚科診療でのデメリットは以下の通りです。
1.触診や詳細な検査、直接的な処置ができない
医師が直接患部に触れて診察したり(触診)、ダーモスコピー(皮膚拡大鏡)などの専門的な機器で詳細に観察したりすることができません。これにより、診断の精度が対面診療に比べて劣る可能性があります。
皮膚の一部を採取して調べる生検や、真菌検査(水虫の検査など)といった検査もできません。
また、患部へ直接医師や看護師が処置をすることもできませんので、ご注意ください。
2.画像による情報不足
オンライン時のビデオカメラで見る患者さんの様子だけでは、その性能に左右されることがあり、情報の読み取りが難しいことがあります。
また、患者さんが撮影した写真や動画の画質、光の当たり具合によって、症状の正確な把握が難しい場合があります。特に、色調の変化や微妙な隆起などは伝わりにくいことがあります。
症状が全身にわたる場合、オンラインですべての部位を詳細に確認することは困難です。
3.重症例や緊急性の高い症状への対応が困難
蜂窩織炎や皮膚感染症、アトピー性皮膚炎、火傷等が重症だった場合など、迅速な診断と治療、あるいは入院が必要となるような緊急性の高い疾患には適していません。
診断が難しい場合や、悪性の可能性が疑われる皮膚腫瘍(ほくろなど)は、オンラインでは判断ができません。
4.通信環境やITスキルが必要
安定したインターネット環境と、スマホやPCの操作スキルが必要です。
通信トラブルがあると診察が中断したり、充分に情報が伝わらなかったりする可能性があります。
現代では、ビデオカメラを活用したオンライン会議等がビジネスでも用いられる機会が多くなり、多くの方にとって一般的でありそんなに難しいことではなくなってきていますが、初めて使う場合戸惑うかもしれません。
5.対応できない疾患や薬がある
依存性の高い薬や、一部の特別な薬はオンライン診療では処方できない場合があります。
また、水虫・カンジダなど、確定診断に検査が不可欠な疾患、自分や介助者が撮影困難な部位が患部の場合など、オンラインでは対応が難しいことがあります。
参照元1:オンライン診療で処方を受けるに当たって注意が必要なお薬一覧
参照元2:⽇本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提⾔
6.費用が別途かかる場合がある
診察及び処方は通常の通院と同じく、保険適用で特別な料金はかかりません。
ただし、オンライン診療システム利用料や、処方箋・薬の郵送料が別途発生する場合があります。これはクリニックによって異なります。ほとんどはクレジット決済です。
皮膚科のオンライン診療なら「おうち病院 オンライン診療」
皮膚の診察は、症状によっては対面診療が必要ですが、軽い症状や経過観察であれば、オンライン診療は向いていることがわかりました。
育児や家事・介護・仕事等で多忙な方、感染症のリスクを避けたい方に、オンライン診療の利用はぜひ検討してほしい方法です。
「おうち病院のオンライン診療」なら、スマホなどから好きな時間を予約できて、お時間になったらオンライン受診できますので、通院のわずらわしさも待ち時間もありません。スキマ時間に受診可能です。
お薬の処方は最寄り薬局の受け取りか自宅配送か選択が可能です。
おうち病院では、全国の大手チェーン薬局と提携しております。ご自宅のそばにあるかは、MAPから確認が可能です。外に出られない事情がある場合などには、自宅配送のおくすりおうち便が喜ばれています。
おうち病院なら、
✅ 通院時間や待ち時間が不要なので体調が悪い時でも安心受診
✅ 初診から保険診療可能
✅ 朝8時〜夜22時まで診察可能 平日夜間・土日祝日いつでも受診可能
✅ スキマ時間で受診できるから、朝の準備中・会議の合間・夜のリラックスタイムにも◎
✅ 予約時間どおりに診察開始だから、朝の準備中・仕事の合間・帰宅後にも受診可能。
✅ 処方せんは指定薬局へ自動送信 全国6,900店舗の薬局で受け取れるから便利
✅ 自宅配送サービス「おくすりおうち便」もあるので、薬局に行く時間がなくても安心

「皮膚トラブルはオンライン診療で大丈夫かな?」と不安ならまずは気軽に相談してみよう
皮膚科のオンライン診療は、特定の疾患や状況において非常に有効な選択肢です。
特に、症状が安定している慢性疾患の継続治療や、軽度の皮膚トラブル、再発性のヘルペスなどには大きなメリットがあります。
仕事や育児・家事など毎日多忙で、なかなか通院できない方の新たな選択肢としておすすめです。
しかし、症状によっては、正確な診断には対面診療や特別な機器を用いての検査が不可欠な場合や、緊急性の高い症状には不向きであることを理解しておきましょう。
「これはオンラインで大丈夫かな?」と迷った場合は、まずはオンライン診療で相談してみるのも良いかもしれません。