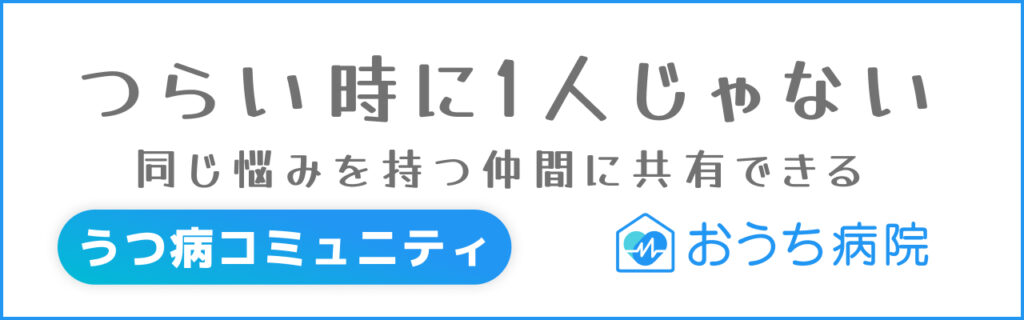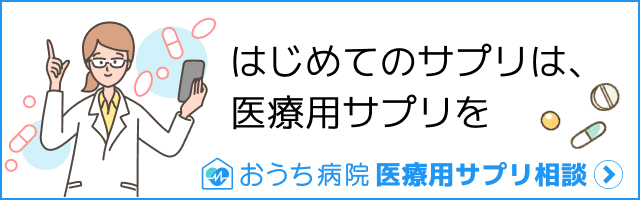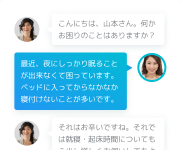うつ病の家族をささえる中で、「目を合わせてくれないけど、どうして?どう接したらいいの?」と対応に戸惑っていませんか?
それは、あなたのことを避けているわけではありません。実はうつ病の初期症状のひとつとして、目つきや表情に変化が現れることがあります。
本記事では、うつ病のサインとしての目の特徴や症状について解説し、家族にできる接し方や対処法などを紹介します。
うつ病による目つき・表情・態度・生活習慣の特徴
うつ病は、目つき・表情・態度・生活習慣に様々な変化をもたらします。
特徴的な変化として、目に生気が感じられなくなる、表情が乏しくなる、集中力や注意力の低下、活動意欲の低下、慢性的な疲労感や睡眠障害などが挙げられます。
これらの変化は、うつ病による心身の症状が外見や行動に現れるものであり、病気のサインとして周囲の人が気づくきっかけにもなります。
目次
うつ病で目を合わせないのはなぜ?
うつ病の人が目を合わせられないのには精神的・身体的な理由が関係しています。
ここではうつ病患者が目を合わせない原因を、心理的な要因と身体的な要因に分けて解説します。
うつ病患者が目を合わせない精神的要因
うつ病患者が人と目を合わせない理由として、ここでは精神的な要因について見てみましょう。
自己否定・罪悪感
うつ病の人は「自分はダメな人間だ」「周囲に迷惑をかけている」と強い自己否定に陥りやすくなります。特に家族や親しい人に対しては、「申し訳ない」「自分のせいで迷惑をかけている」と感じやすく、目を合わせることも精神的な負担になってしまいます。
「自分には価値がない」「どうせ私なんて・・・」と自己否定感や罪悪感が高まることで人と目を合わせることが困難になり、他者との関わり自体も避けるようになっていきます。
過敏な不安感
うつ病の人は不安感が過剰に強まり、他人の視線を過剰に気にするようになります。他者の目を「評価されている(ジャッジされる、自分は下に見られている)」「責められている」などと否定的に捉えてしまい、「見られたくない」「どう思われているのか怖い」と不安や恐れから無意識のうちに目を避けてしまうことがあります。
この過敏な反応は社会不安障害の症状とも類似しており、対人関係をより困難にする要因となります。
うつ病患者が目を合わせない身体的要因
目を合わせないのは、うつ病の症状による身体的な要因も大きく影響しています。
過剰な疲労感・エネルギー不足
うつ病は心だけでなく、身体のエネルギーも大きく消耗させます。常に強い疲労感や倦怠感を感じ、日常の些細な動作でさえも負担に感じることが増えます。目を合わせるという行為も例外ではなく、相手の視線を意識するだけで疲れてしまうことがあります。
慢性的に疲労感が強くエネルギー不足の状態が続くため、他者との関わりや視線を合わせることを避けるようになります。
集中力・注意力の低下
うつ病では脳の働きが鈍くなり、思考力や判断力が低下しやすくなります。
会話の内容が頭に入らなかったり、理解するのに時間がかかったりするようになり、相手の目を見ながら話す余裕もなくなっていきます。特に複雑な話や長い会話になると、集中力が続かずに視線を落としてしまうこともあるでしょう。
相手の話に関心がないわけではなく、脳のエネルギーが低下しているために起こる現象です。
うつ病患者が目を合わせないことは単なる気分の問題ではなく、精神的・身体的な要因が複合的に関係した結果の症状です。
その他、目に関連するうつ病の症状
うつ病は気分の落ち込みや意欲の低下だけでなく、身体にもさまざまな影響を及ぼします。その中でも、目に現れる症状は見落とされがちですが重要なサインです。ここでは、うつ病による目の異常や不調について解説します。
目がうつろになる、焦点が合わない
うつ病の人は、目の焦点が合わず、ぼんやりとしていることがあります。
これは脳のエネルギー不足や意欲低下によるものと考えられます。特に強い疲労感や思考力の低下が伴う場合、目の動きが鈍くなり、無意識のうちに焦点を合わせることが困難になることがあります。
それを見ていると「目がうつろで様子が変だ」「話を聞いていないのではないか」などと思われるかもしれませんが、本人は意図的にそうしているわけではありません。
目つき(表情)が変わった
うつ病になると顔の表情が乏しくなり、目つきが変わったように見えることがあります。
うつ病の代表的な症状として感情鈍麻(喜怒哀楽の感情が鈍くなり、感情表現が乏しくなる症状)が起こると、表情筋の動きも少なくなり表情も乏しくなっていきます。気力の低下により、視線を上げることさえ億劫に感じることもあります。
そのため、目の周りの筋肉が緩み、まぶたが重く垂れ下がったような印象を与えることがあります。
目の疲労感がなかなか取れない
うつ病の影響で、目の疲労感が慢性的に続くことがあります。
原因としては、自律神経の乱れや睡眠の質の低下などが考えられます。
また、身体的な疲れだけではなく、精神的なストレスも疲労感を強める要因となります。うつ病では目に限らず全身の疲労感が慢性化しやすいため、通常の休息では改善しにくく、長期間続くことが特徴です。
こうした持続的な疲労感は、日常生活の質を著しく低下させる要因となります。
目の痛みや重さを感じる
うつ病では、目の奥の痛みやまぶたの重さを訴える人も少なくありません。
これは交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、血流が悪くなることで生じると考えられます。
また、ストレスや疲労の蓄積により目の周りの筋肉がこわばりやすく、ときには痛みが生じることもあります。この症状は患者の不快感を増大させ、さらなるストレスの原因となる可能性があります。
視界のぼやけ
うつ病になると、視界がぼやけたり、かすんだりといった症状が現れることがあります。
この症状は目の疾患ではなく、精神的なストレスや自律神経の乱れが原因であることが多いです。特に、強い不安感や疲労を感じているときに起こりやすく、目の焦点を調整する筋肉の機能が低下することで生じます。
目の潤いも不足しやすく、ドライアイのような症状を引き起こすこともあります。
うつ病で目を合わせない家族への接し方
「目も合わせてくれない」「これまでと様子が明らかに違う・・・」とうつ病になった家族への接し方に戸惑う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、家族としてできる接し方や具体的な支援方法について解説していきます。
無理に目を合わせようとしない
うつ病の方は、視線を逸らしていても実は会話の内容を聞いていることが多いです。視線を避けられたり反応が薄かったりすると「話を聞いていないのでは?」と不安になるかもしれませんが、無理に目を合わせようとすると、余計にプレッシャーを与えてしまいかねません。
目が合うかどうかよりも大切なのは、関心を持っていることを伝える姿勢や安心できる雰囲気づくりです。穏やかな声で話しかけ、相手のペースを尊重しましょう。反応が少なく見えても、相槌や短い返事が返ってくるだけでも充分です。
安心感を伝える言葉がけ
うつ病の人は「自分は一人だ」「誰にも理解されない」と感じやすくなっています。そんなとき、家族や周囲の人の言葉が支えになります。「無理しなくていいよ」「そばにいるからね」「何かあったら話してね」と寄り添う気持ちを言葉で伝えることで、心の安全基地をつくることにつながります。
また、相手を励まそうとしすぎないことも大切です。「頑張って」といった励ましの言葉は、うつ病の人にとって負担となりやすいため避けるようにしましょう。
目を合わせなくていいコミュニケーション
目を合わせるのが難しい場合は、横並びでの会話がおすすめです。
散歩やドライブ、食事中など、目を合わせなくても自然と話せる状況を活用しましょう。正面から向き合うよりもお互いにリラックスしやすく、会話のハードルが下がります。
また、話すことにこだわらず一緒にテレビを観たり、音楽を聴いたりするだけでも安心感につながります。言葉を交わさなくても、そばで過ごす時間を増やすことで寄り添う気持ちが伝わります。
受診や専門的な支援を促す
うつ病は適切な治療によって回復が期待できますが、受診のハードルが特に高い病気です。
家族がストレートに「病院に行ったほうがいい」と言うと、抵抗感を持たれることがあります。「最近しんどそうだけど、大丈夫?詳しい人に相談してみるのはどう?」など、本人の気持ちに寄り添いながら提案しましょう。
心療内科や精神科では、薬物療法やカウンセリングを通じて、少しずつ症状を改善していくことができます。また、薬に抵抗がある場合には、サプリメント療法などの選択肢についても検討してみましょう。
目を合わせない家族のうつ病治療をサポートするサプリメント
うつ病の治療には栄養面からのアプローチも有効です。
症状改善を促す栄養素を適切に摂取することで、回復の促進につながります。食事から摂れるのが理想ですが、食事だけで摂取することは現実的には難しいため、サプリメントを活用した栄養補給が効果的です。特に「できるだけ薬に頼りたくない」と考える方には、栄養バランスの改善に役立つ可能性があります。
ここでは、うつ病改善をサポートするとされる栄養素や摂取できる食品について解説します。
関連記事:うつ病をサポートするサプリ選び|栄養補給で心のケアを
オメガ3脂肪酸
オメガ3脂肪酸は脳の健康維持に重要な成分で、そのうちのDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)には抗うつ作用が期待されています。
これらの成分が神経細胞の膜を柔軟な状態に保ち、情報伝達をスムーズにします。これにより動脈硬化や血栓予防・脳の機能改善、炎症の軽減などをはじめ、気分・感情の安定にもつながるといわれています。
オメガ3脂肪酸が不足すると、うつ病のリスクが高まるという研究データもあります。
| おすすめの食品 | サバ・イワシ・サンマなどの青魚、亜麻仁油、チアシードなど |
| サプリメント活用のポイント | 魚を頻繁に食べるのが難しい場合は、DHA・EPA配合のサプリを利用すると効果的 |
ビタミンD
ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨を丈夫にするホルモンです。
同時に神経伝達を助ける働きがあり、免疫機能の調節や精神のバランスを整える作用があるため、不足すると気分の落ち込みやうつ状態に陥るリスクが高まります。日光を浴びることで体内で合成されるため、屋内にこもりがちな人は不足しやすくなります。
冬になると日照時間が減るため、季節性うつ(冬季うつ)が増える原因にもなります。
| おすすめの食品 | サケ・マグロ・サバなどの魚類、卵黄、キノコ類など |
| 日光浴のポイント | 1日15~30分、意識して日光を浴びる習慣をつけると、体内のビタミンDの合成を促進する |
ビタミンB群
ビタミンB群は神経伝達物質の生成に関わる成分で、脳の機能をサポートします。その中でも特に気分の安定やストレス耐性の向上に関与しているといわれる成分がビタミンB1・B6・B12、葉酸です。
これらはストレス緩和やうつ病の予防に役立つことが知られています。豆類、緑黄色野菜、魚介類などに豊富に含まれていますが、食事からの充分な摂取が難しい場合はサプリメントを利用するのも一つの方法です。
| おすすめの食品 | 豚肉、レバー、卵、大豆製品、バナナ、ほうれん草など |
| サプリメント活用のポイント | 水溶性ビタミン(※一度にたくさん摂取しても尿中に排泄される成分)のため、こまめな摂取が必要。食事からの定期的な摂取が難しい場合にはサプリメントで補うのがおすすめ |
マグネシウム
マグネシウムは骨や歯の形成・維持に役立つ成分で、筋肉の収縮、体温や血圧の調整などの働きがあります。神経情報の伝達をサポートする成分でもあり、適切に摂取することでリラックス効果やストレス軽減が期待できます。
低マグネシウム血症の人は、サプリメントによるマグネシウム補給がストレス軽減に効果的であるとされています。
| おすすめの食品 | ナッツ類(アーモンド・カシューナッツ)、海藻類、玄米、大豆製品、バナナなど |
| サプリメント活用のポイント | 食事で摂りにくい場合は、マグネシウム配合のサプリメント利用がおすすめ。過剰摂取するとお腹が緩くなることがあるため、適量を守ることが大切。 |
L-トリプトファン
L-トリプトファンは、幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンや、メラトニン(睡眠に関わるホルモン)の材料となるアミノ酸の一種です。
特にセロトニン不足はうつ病の原因のひとつともいわれており、セロトニンが不足すると気分の落ち込みやイライラ、不眠の原因にもなるため、トリプトファンを適切に摂取することが重要です。
| おすすめの食品 | 牛乳・ヨーグルト・チーズなどの乳製品、卵、大豆製品、バナナ、ナッツ類 |
| サプリメント活用のポイント | 睡眠の質を改善したい場合には、夜に摂取すると効果的。単体で摂るよりも、ビタミンB6と一緒に摂ることで、セロトニンの合成が促進される。 |
うつ病の改善には栄養バランスを整えることも大切です。毎日の食事を見直しながら、必要に応じてサプリメントを活用していきましょう。
うつ病治療をサポートするサプリメント利用なら、おうち病院「オンラインサプリ相談」
うつ病ケアでサプリメントを取り入れるなら、ぜひ医療用サプリメントを検討してみてはいかがでしょうか。
医療用サプリメントは、市販品のように自己判断で買えるものではなく、医師の診断が必要になります。
どんな治療が望ましく、どの成分のサプリメントが治療をサポートしてくれるのか、症状や体質に合わせて医師が判断してくれます。
また、通院は面倒、恥ずかしい、気が重い、うつかなと思っても多忙で時間が取れない、などのご事情があれば、「おうち病院 オンラインサプリ相談」を試してみてはいかがでしょうか。
おうち病院なら、
✅栄養学やサプリメントに精通したおうち病院所属医師が対応
✅医療機関専用サプリをオンラインで処方・購入可能(通院時間や待ち時間が不要)
✅医療機関で必要とされる高配合量で製造されたサプリメント
✅安心品質 国内大手の医療機関専用サプリメントメーカーとの提携
✅体調などで気になることがあっても安心 24h365日オンラインで対応可能
「おうち病院 オンラインサプリ相談」なら、病院を受診する時間がなかなかとれないという人でも、医療機関専用サプリメントをオンラインで処方・購入可能です。
初めてサプリメントの購入を検討している方は気軽に、既にサプリメントを服用している方はいつものサプリメントを医療品質に。
ぜひ「おうち病院 オンラインサプリ相談」をご利用してみてください。
1人で抱え込まずに、うつ病患者の家族をサポートするコミュニティの活用を
家族がうつ病になったとき、患者本人だけではなく、サポートする家族の方も一人で悩みを抱え込まないことが大切です。一人で悩み続けるとささえる側の心も疲弊し、共倒れになってしまうことがあります。
そんなとき、同じような経験をしている人と励まし合い、相談し合うことで、心の負担の軽減を図れます。うつ病のケア方法や接し方についても、実体験に基づいた情報交換ができる場があれば安心につながります。
うつ病患者の家族の方におすすめしたいのが「おうち病院 疾患コミュニティ」です。
「おうち病院 疾患コミュニティ」は、専門家のアドバイスを受けられることに加え、同じ境遇の人とつながることができるオンラインのコミュニティです。患者・家族がそれまでに吐き出せなかった悩みや苦悩を吐き出したり励まし合ったりできる環境です。登録は無料で、気軽に参加できます。
うつ病患者の家族も、適切なサポートを受けながら自分の心の健康を守ることが大切です。ぜひ「おうち病院 疾患コミュニティ」を活用してみてください。
目を合わせないうつ病の家族が心配な時は、同じ境遇の人と励まし合い情報交換しよう
家族や大切な人がうつ病になると、どう接していいかわからず戸惑う方も多いでしょう。目も合わせなくなったり目つきが変わったりなど心配な症状が現れると、より一層不安も大きくなるのではないでしょうか。
そんなとき、同じ悩みを持った人と励まし合い、相談し合える環境があることは心の支えになります。コミュニティを通じて経験や知識を共有し、互いにサポートし合うことは、うつ病患者とその家族の生活の質の向上につながります。
一人で悩まず、ぜひ「おうち病院 疾患コミュニティ」をご活用ください。