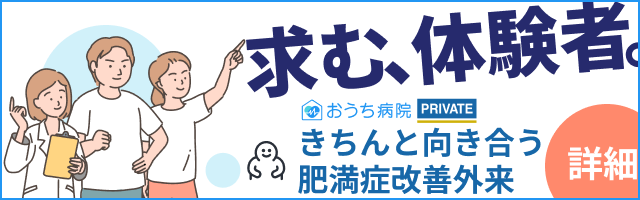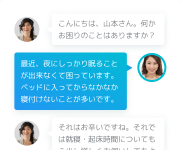「ダイエットをしているのに、なかなか体重が減らない…」とお悩みではありませんか?「運動をしても痩せない」と悩んでいる人も多いかもしれません。
頑張っても結果が出ないと、モチベーションが下がってしまいますよね。そこで本記事では、ダイエットをしても体重が減らない原因と対策を解説します。
目次
ダイエット中に体重が減らないのはなぜか?
ダイエット中に体重が減らない原因は、いくつか考えられます。まずは、原因を探っていきましょう。
原因1.消費カロリーが足りていない
ダイエット中に体重が減らないときは、消費カロリーよりも摂取カロリーが上回っているからかもしれません。
食事を摂る際、自分で思っているよりもカロリーを摂取していることがあります。
また、運動量が少なすぎて、摂取カロリーが消費カロリーを上回っている可能性もあるでしょう。
正しい摂取カロリーは「基礎代謝量×身体活動レベル」の計算式(※)で算出できます。
たとえば体重が約52kgの25歳の女性なら、1日の基礎代謝量は1,090kcalです。そして生活の大部分を座って過ごす場合、活動レベルは1.50となります。計算式に当てはめて算出したカロリーは、1,090×1.50=1,635kcalです。
体温や生活環境などさまざまな要素によって変動しますが、上記の場合は大体1,600kcal以上摂取すれば適正体重より太り、1,600kcal以下であれば痩せていきます。
※参照元:1日に必要なカロリー/推定エネルギー必要量|日本医師会
原因2.血糖値が乱れる食べ方をしている
血糖値が乱れる食べ方をしている場合も、ダイエット中に体重が減らない原因になります。
たとえば、早食いが癖になっていたり、GI値が高い食べ物を好んでいたりする場合などは、血糖値が乱高下しやすいです。
GI値とは、血糖値の上げやすさを表す指数のことです。
カロリーが同じものでも、GI値が高い食品の方が太りやすい傾向にあります。
また、血糖値が急上昇すると、インスリンによって余計な血中のブドウ糖が脂肪として取り込まれます。その後血糖値が急降下すると空腹感を強く感じ、食べすぎるという悪循環に陥りやすくなる可能性があります。
原因3.基礎代謝が低い
ダイエット中に体重が減らない原因のひとつに、基礎代謝が低い点も挙げられます。
基礎代謝とは、何もしていなくても生命維持のために消費されるエネルギーのことです。
基礎代謝量が低いと、もともとの消費カロリーが少ないため、同じ摂取カロリー量でも痩せにくい可能性があります。
基礎代謝は個人の筋肉量や年齢、生活環境(例えばデスクワークか立ち仕事か)、体質(冷え性・低体温の人は代謝が低め)などによって異なります。
一般的に10代後半をピークに基礎代謝は低下し、40代以降は筋肉量減少に伴って基礎代謝量も下がる傾向があるでしょう。
運動習慣がなく筋肉量が少ない人や、高齢の人は特に基礎代謝が低めの傾向にあるため、摂取カロリーを減らしても体重が減らない場合もあります。
原因4.むくみや便秘
むくみや便秘も、ダイエット中に体重が減らない原因のひとつです。
体内の水分バランスやお通じの状況によって、一時的に体重が落ちにくい場合があります。
特に女性は月経周期の影響で、むくみやすい時期とそうでない時期があります。
女性の体は月経前になると黄体ホルモン(プロゲステロン)の作用で水分や塩分をため込みやすくなり、むくんで体重が増えやすくなるのが特徴です。
また、塩分の摂り過ぎも体が濃度を薄めようと水分を溜め込むため、むくみの原因になる可能性があるでしょう。
厳しい食事制限により食物繊維や油分が不足することで便の総量が減り、便秘になりやすくなることもあります。
そのため、便が腸内に長く留まる分、体重が増えたと感じる可能性もあります。
原因5.筋肉量が増えている
運動をする機会が多い場合(特に積極的に筋トレを行っている場合)は、体重計の数字が減らないどころか少し増えることがあります。
同じ体積でも脂肪より筋肉の方が重いため、筋肉が増えることで体重が増えた(太った)と感じる場合があるでしょう。
これは、これまで筋トレをしてこなかった人が始めた直後や、筋トレに慣れてきてトレーニングの強度を上げた際に起こりやすい現象です。
筋トレや運動を増やした実感がある場合、体重の数値だけで一喜一憂するのではなく体脂肪率や身体のサイズ、見た目の引き締まり具合などもチェックしてみるとよいでしょう。
筋肉が増えて体脂肪が減っているのであれば、健康面においてもメリットが大きいです。
原因6.睡眠不足
睡眠不足は食欲に関するホルモンバランスを崩し、食欲増進につながります。
そのため、思いがけず食べ過ぎてしまい、ダイエットをしていてもなかなか体重が減らないことがあるでしょう。
睡眠が不足すると本来食欲を抑える作用のあるレプチンというホルモンの分泌が減り、反対に食欲を刺激するグレリンというホルモンが増加します。
その結果、満腹感を感じにくくなり、食欲をコントロールできずについ食べ過ぎてしまうケースがあります。
実際に、睡眠時間が短い人は食欲が増して太りやすいという研究報告もあります。
さらに、慢性的な睡眠不足はストレスにつながることもあります。
睡眠不足の際なんとなくダラダラ食べ続けてしまったり、過食してしまったりする場合は、ホルモンが影響しているかもしれません。
原因7.加齢の影響
ダイエットをしているのに体重が減らない際は、加齢が影響している可能性もあります。
年齢とともに痩せにくくなるのは、基礎代謝やホルモン分泌、自律神経の働きが変化するためです。
10代や20代の頃は、太ったと感じても少し食事を制限すれば、すぐに体重が戻った人も多いかもしれません。
しかし、年齢とともに痩せにくくなる傾向にあります。
若い頃は自律神経やホルモンの働きで、食べたらすぐ脂肪を燃焼する反応(食事誘発性熱産生など)が活発ですが、加齢によりその機能が衰えていくためです。
また、筋肉量も年齢とともに減少する傾向にあります。
そのため、基礎代謝が低下し、「若い頃と同じ生活をしているのに太る」といった現象が起こりやすくなります。
原因8.ストレス
ストレスは、ダイエットの大敵です。
精神的なストレスがかかると、体はそれに対処しようとしてストレスホルモンである「コルチゾール」を分泌します。
コルチゾールは食欲抑制に関わる神経伝達物質「セロトニン」の分泌を抑制するため、食欲のブレーキが利かなくなって過食に走りやすくなることも。
加えて、コルチゾールには血糖値を上げる作用もあります。血糖値が上がると、インスリンが分泌されます。
余分な血糖がインスリンの働きによって脂肪として蓄積されやすくなることで、なかなか体重が減らない場合もあるかもしれません。
参照元:「ストレス」と「肥満」の関係|けんぽだよりWeb | 首都圏デジタル産業健康保険組合
原因9. 停滞期に入っている
これまで順調に体重が減っていたのに急に減らなくなった場合は、「停滞期」の可能性があります。
停滞期とは、ダイエットをしていても体重が減らなくなる期間のことです。
人には「ホメオスタシス(ホメオスターシス:恒常性維持)」と呼ばれる、生命の維持に必要な機能を保とうとする機能が備わっています。
そのため、ダイエットで体重が減少すると、ホメオスタシスにより体が元に戻ろう(現状維持)として、体重が減らなくなることがあります。
個人差はありますが、1カ月以内に体重が約5%減少したタイミングでホメオスタシスが最大限に働き、約1カ月程度持続すると言われています。
そのため、月0.5〜1キロなど、ゆるやかに無理なく体重を減らしていくのがおすすめです。
また、ダイエットを始めてしばらくすると、体は少ないエネルギー量で活動することに慣れていきます。その結果、基礎代謝が低下して体重が減らないケースもあります。
ダイエットしているのに体重が減らないときの対策
ダイエットをしているのに体重が減らないときの対策を紹介します。なかなか体重が減らず悩んでいる人は、さっそく実践してみましょう。
消費カロリーと摂取カロリーを把握する
ダイエットをしているのになかなか体重が減らないときは、まず1日の消費カロリーと摂取カロリーを把握するとよいでしょう。
自分では食べていないつもりでも、記録してみると意外と量を食べているケースがあります。間食や飲み物のカロリーを見逃している場合もあるかもしれません。
摂取カロリーは、野菜や肉、米などの素材以外に、調味料も含めて記録するのがおすすめです。
記録の際は、スマートフォンのダイエットアプリなどを活用するとよいでしょう。また、消費カロリーはスマートウォッチなどを活用すれば把握しやすいです。
ただし、記録に神経質になりすぎると長続きしません。自分ができる範囲で続けるとよいでしょう。
栄養バランスの良い食事を摂る
栄養バランスの良い食事を心がけるのも大切です。
糖質や脂質を「太りやすいから」といって極端に制限すると、一時的に体重が減ってもリバウンドをしたり健康を損ねやすかったりするため注意が必要。
食事制限の際も、人間の体に必要な三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)とビタミンやミネラル、食物繊維をバランス良く摂ることが基本です。
必要な栄養を摂りつつも、塩分を控えてカリウムが多く含まれる果物や野菜、水分を意識的に多く摂取するのがおすすめ。便秘の予防や解消につながります。
血糖値が穏やかになる食べ方をする
食べる順番や食品の種類を意識すると、食後血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。
食事の最初に食物繊維の多い野菜類を食べる「ベジファースト」を実践すると、食後の血糖値が急上昇しにくくなります。
また、食事の際はできるだけGI値が低い食品を選ぶのもよいでしょう。一度に大量の糖質を摂ると血糖値の急上昇・急降下(血糖スパイク)を引き起こす可能性があります。そのため、間食の際はナッツやヨーグルトなどの低GI食品や高タンパクのおやつを少量摂取する程度に留めるのがおすすめです。
よく噛んでゆっくり食べるのも大切なポイント。ゆっくり食べることで適切にインスリンの分泌が行われるため、血糖値の乱高下を防げるでしょう。
低GI値食品例
玄米、全粒粉パン、蕎麦、野菜(ブロッコリー・キャベツ・ピーマン・玉ねぎ)、きのこ類、豆類、牛乳、バター、肉類、魚介類、フルーツ(りんご、いちご)など
参照元:GI値とは?食品のGI値や体に与える影響をわかりやすく解説|北海道科学大学
基礎代謝をあげる
基礎代謝を上げるのも有効です。基礎代謝を上げるには、筋肉量を増やすのがポイント。
筋肉は基礎代謝を上げる役割を持っています。そのため、日常生活に適度な運動を取り入れることで筋肉量の減少を食い止め、基礎代謝を維持することができるでしょう。
運動をする際は、有酸素運動(ウォーキングやジョギング等)と筋力トレーニングをバランス良く組み合わせるのがおすすめ。
あわせて、筋肉の材料となるタンパク質をしっかり摂るのも大切です。
さらに、体を冷やさないようにするのも基礎代謝をあげる際に気をつけたいポイントです。
薄着で体を冷やしすぎたり真夏に冷房が効きすぎた環境に長時間いたりすると、体温維持のためのエネルギー消費が減って代謝が下がる場合があります。
月経周期を考慮する
女性の場合は、月経周期に合わせてダイエットを計画するとよいでしょう。
月経前はホルモンの影響で食欲が増し、体に水分を溜め込みやすい時期です。そのためこの時期に無理に食事を我慢すると、ストレスになって過食につながるケースもあります。無理せず食事内容に工夫をしながら過食にならないよう過ごすとよいでしょう。
また、月経中は体がむくみやすく体重が落ちづらい時期と認識し、この時期の体重の変動は気にしないようにしましょう。体調不良を感じる際は、無理せずダイエットを休む選択も必要です。
一方で、月経が終わった直後は、エストロゲンと呼ばれるホルモンの分泌が増えて代謝があがります。
そのため、ダイエットの効果も出やすい時期です。積極的に運動やカロリーコントロールに取り組むとよいでしょう。
睡眠をしっかりとる
良質な睡眠と充分な睡眠時間の確保は、ダイエットの強い味方です。
そして良質な睡眠をとるためには、就寝1時間前はリラックスする時間をもうけるとよいでしょう。
その際、スマートフォンやパソコンの使用は控えるのがおすすめ。
就寝前にスマートフォンやパソコンを使用すると、画面から発せられるブルーライトが脳を刺激して、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制される可能性があるためです。
また、カフェインや喫煙、過度な飲酒も睡眠の質を下げる原因になるため、就寝前は控えましょう。
寝室はリラックスできる環境に整え、遮光性の高いカーテンを使用するといった工夫もするとよいかもしれません。
生活習慣を見直す
加齢による代謝の低下や自律神経の乱れは、生活習慣を正すことである程度カバーできる可能性があります。
そのため、健康的に痩せるためには規則正しい生活を心掛けるとよいでしょう。
毎日の起床時間と就寝時間をできるだけ一定にすることは、体内時計(概日リズム)を整えて自律神経を正常な状態にし、基礎代謝を維持する基本です。
食事も3食なるべく同じ時間帯に規則正しく摂るのが理想です。遅い時間の食事は脂肪を蓄積しやすいので、夕食はできれば20時頃までに済ませるとよいでしょう。
仕事などでどうしても20時前に食事を摂るのが難しい場合は、ランチでしっかり目に食べて夜は少なくしたり、消化の良いものやタンパク質中心の軽めの食事で済ませたりする工夫をするとよいでしょう。
さらに、一日中だらだら過ごすのではなく、こまめに家事をしたり散歩に出たりなど、なるべく体を動かすことを意識するのもポイントです。
ストレス管理
ストレスを溜めない工夫も大切です。ストレスを溜めるとホルモンバランスが乱れ、過食につながったり代謝が落ちたりする可能性があります。
食事から離れた趣味や好きなことでストレス解消しましょう。
食べることでストレスを解消するのは一時的な気晴らしになるものの、その後の罪悪感やダイエットのモチベーション低下につながるかもしれません。
リフレッシュには深呼吸やストレッチ、軽い運動などがおすすめです。ほかにも趣味に没頭する時間を作ったり、友人と話したりするのもよいでしょう。
上手にストレスを発散して、心身のバランスを保つことが大切です。
チートデイを設ける
週に1回程度「チートデイ」を設けるのもよいでしょう。
チートデイとは、好きなものを気にせずなんでも食べて良い日です。体重が減らなくなる停滞期は、低エネルギー状態に慣れた体が省エネモードに入っている状態です。
体が「飢餓状態である」と感じているため、チートデイの日にはいつもより多めにカロリーを摂取することで「飢餓状態ではない」と身体に知らせるのです。
普段食べたいものを我慢している分リフレッシュになり、ダイエットへのモチベーションも上がるかもしれません。
チートデイの際は好きなものを食べて問題ありませんが、できるだけ栄養バランスを意識することをおすすめします。
ダイエットしているのに体重が減らないと悩んだら「専門家に頼る」という選択肢もあり
間違ったダイエット方法を続けると、筋肉量の低下や貧血、月経異常、骨粗しょう症など健康を損なうリスクがあります。
そのため、自己流のダイエットで限界を感じたら、専門家に相談するのも手です。
たとえば、運動や筋トレならスポーツジムのパーソナルトレーナーの指導を受ければ、自分に合った筋トレや有酸素運動の方法を教えてもらえます。
ファスティング(断食)に興味があるなら、断食道場や専門の指導者のもとで正しいやり方を学ぶとよいでしょう。
食事管理が難しいと感じる場合は、管理栄養士による栄養指導や医療機関での食事療法プログラムを利用する方法もあります。
また、BMIが25以上の肥満で高血圧や糖尿病など生活習慣病のリスクがある場合は、医師の管理下での減量治療(肥満症治療)も選択肢のひとつです。
体重が減らなくて悩んでいるなら、医療ダイエットに向いている場合も
「いくら頑張っても痩せない」「健康診断で肥満を指摘され、健康リスクが心配」など自己流ダイエットに限界を感じた場合は、医療ダイエットに向いているかもしれません。
医療ダイエットがおすすめの方
医療ダイエットに向いている方は、健康上の理由でダイエットの必要がある人です。
具体的には、肥満が原因で高血圧や糖尿病など何らかの健康障害を抱えている人や、健康障害に発展するリスクが高い「肥満症」と診断された人を指します。
上記に該当する場合は、保険適用で肥満症の治療薬を処方してもらえる可能性があります。
肥満症の定義は、BMI(体格指数)が25以上で肥満が原因で発症する11種の健康障害のいずれかを合併しているか、高度な内臓脂肪蓄積(腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上)がある場合です。
また、肥満症の診断がつかない場合でも、放置すると将来的に健康リスクにつながりそうな「BMI指数が肥満になる人」の場合は、自由診療で肥満症の治療薬を処方する病院もあります。
医療ダイエットによる治療方法・治療薬
医療機関で行われる肥満症治療(医療ダイエット)の基本は、まず食事療法・運動療法など、生活習慣の改善です。
これに加え、必要に応じて薬物療法が検討されるケースもあります。
日本で保険適用となっている肥満症治療薬には以下のようなものがあります。
食欲抑制剤(マジンドール(サノレックス)など)
食欲を抑える内服薬です。脳の視床下部に作用して満腹中枢を刺激するため、空腹感を感じづらくするのが特徴。
GLP-1受容体作動薬(セマグルチド(ウゴービ)など)
糖尿病治療薬として開発された薬です。食後血糖値の上昇を抑えるため、満腹感を持続させやすくなります。週に1回、自己注射を行うことで効果を発揮します。
SGLT2阻害薬(経口薬)
糖尿病患者に処方される薬です。腎臓からブドウ糖を尿に排泄させることで、血糖値を下げる働きをします。肥満症単独の適応は無く、あくまで糖尿病の治療として処方され、結果的に体重減少が得られます。
漢方薬
肥満症治療に保険適用で使われる漢方薬として、「防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)」「防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)」「大柴胡湯(だいさいことう)」などがあります。
ダイエットの相談可能なクリニック
ダイエットに関する悩みは、一般の内科や専門外来で相談できます。
まずはかかりつけの内科医に相談すれば、必要に応じて生活習慣病外来や肥満症外来、ダイエット外来などを紹介してもらえるでしょう。
最近では、オンライン診療で肥満症の相談・治療を行うクリニックでもダイエットの相談をすることが可能です。
オンライン診療の場合はWebで問診票を入力し、ビデオ通話やチャットを通じて医師からアドバイスを受け、必要な薬があれば郵送処方してもらえるサービスもあります。
症状によって血液検査や画像検査が必要と判断されれば、対面診療をすすめられる場合もあります。
ウゴービなど自己注射の治療薬を処方された場合は、自己注射の指導をオンライン上で行うことも可能です。
忙しくてなかなか通院できない人や、他の患者もいる中での受診に抵抗がある方にとってはオンライン診療が心強い選択肢となるでしょう。
肥満症薬の処方なら「おうち病院Privateシリーズ きちんと向き合う肥満症改善外来」
肥満や過体重は、高血圧・糖尿病・脂質異常症など、さまざまな生活習慣病のリスク因子となります。
運動や食事に気を配っているつもりでも、加齢やホルモンバランスの変化、ストレスなどの影響で、思うように体重が落ちないと感じている方も多いのではないでしょうか。
そのような方には、医師の継続的な診察とサポートを受けながら、医療的介入(薬物治療)と生活習慣の見直しを組み合わせた治療が推奨されます。
「他サービスのように、お薬の処方だけで終わりでは不安…」そんな声に応えるのが、「おうち病院Privateシリーズ きちんと向き合う肥満症改善外来」です。
「おうち病院 きちんと向き合う肥満症改善外来」なら、
✅ 1回30分の診察時間を確保:患者様の背景や課題を丁寧にヒアリングし、きめ細かい治療方針を提案
✅ リバウンド防止にも対応:体重減少後も、生活習慣改善の継続支援あり
✅ 平日・土日祝すべて対応:朝8時〜夜22時まで診察可能
✅ 診察後、薬はご自宅に配送:通院不要で治療継続がしやすい
✅ 予約時間ぴったりに診察開始:出社前、会議の合間、就寝前など、スキマ時間で受診可能
「きちんと向き合う肥満症改善外来」では、自宅にいながら専門医の診察を受け、必要なお薬は自宅へ配送されます。忙しい方でも、医療の力を味方につけて無理なく継続できる環境を整えています。
なお、初回受診時には医師が正確に状態を把握するため、「健康診断書」または「体重計測結果の画像」のご提出が必要です。ご予約の前にご用意いただくようお願いいたします。
本気で体重改善に取り組みたい方、自己流のダイエットに限界を感じている方は、
ぜひ「おうち病院 きっちり向き合う肥満症改善外来」での診察をご検討ください。
ダイエット中に体重が減らなくて限界を感じたら、医師に相談してみよう
ダイエットをしていても体重が減らない原因は、人によって異なります。さらに、原因は一つではなく、いくつかが複雑に絡み合っている場合もあるでしょう。
自己流ダイエットに限界を感じた際には、無理せず専門家の手を借りるのがおすすめです。
また、健康診断で「肥満」や「メタボリックシンドローム」に該当すると指摘された場合も、そのまま放置せず医療ダイエットを検討してみてもよいかもしれません。
医師や管理栄養士の力を借りれば、健康を損なうリスクを減らしながら効率よく体重を落とす方法が見つかるはずです。
多忙でなかなか通院する時間がとれない、家や勤務先の近くに適切なクリニックがないなどお悩みの方は、ぜひ「おうち病院 きちんと向き合う肥満症改善外来」で一度相談してみてはいかがでしょうか。