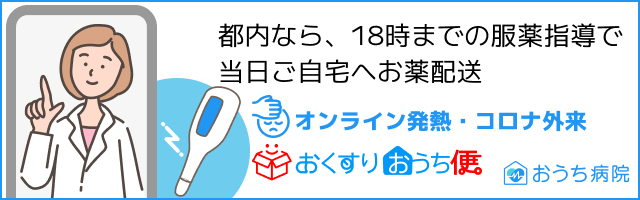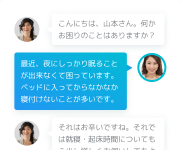新型コロナウイルス感染症は軽症であれば自然治癒することが多いです。しかし基礎疾患のある方は重症化リスクが高いため、治療のために適切な治療薬を使用することが大切です。
新型コロナウイルス感染症の治療薬は複数あり、それぞれで効果や対象となる方が異なります。また治療薬によっては使用禁忌となる方や併用禁忌の薬もあるため注意が必要です。
事前に治療薬について理解を深めておけば、安心して新型コロナウイルス感染症の治療を受けられます。
今回は、日本において承認されている10種類の新型コロナウイルス感染症の治療薬の種類や目的、効果などについて解説していきます。
もしコロナで病院に行くのもつらいという方は、オンライン診療という手段もあります。「おうち病院 オンライン発熱・コロナ外来」なら、自宅で受診の上薬を受け取ることができますので、ぜひご利用ください。
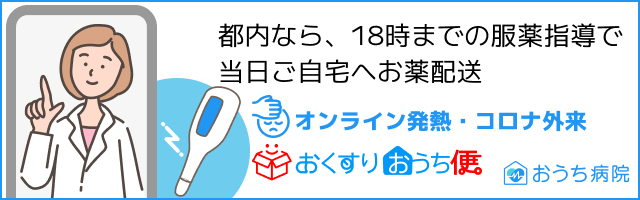
目次
コロナの特効薬は存在しない
新型コロナウイルス感染症に有効な特効薬は、現在のところ存在していません。
感染症は細菌やウイルスなどの病原体が身体に侵入することで症状が現れます。細菌が原因の感染症であれば、抗菌薬により治療できます。しかし、ウイルスは細菌と大きさや仕組みが異なり、抗ウイルス薬は少数しかありません。もちろん、新型コロナウイルスの特効薬も残念ながら開発されていないのが現状です。
そのようなことから新型コロナ治療では、他の疾患治療で使われている既存薬を転用して使用することが多いです。既存薬の使用は、症状の緩和や重症化リスクを抑えることが目的であるため、軽症で重症化リスクの低い方であれば使用されないことがほとんどです。
治療薬の種類と目的
令和5年4月1日現在、厚生労働省にて新型コロナウイルスの治療薬として承認を受けているのは10種類あります。それらのコロナ治療薬は目的に応じて「抗炎症薬」「抗ウイルス薬」「中和抗体薬」の3つに分けることができます。
「抗炎症薬」は、新型コロナウイルス感染症の重症化で起こる、過剰な免疫反応を抑制する目的で使われます。「抗ウイルス薬」はウイルスの増殖を抑えることで、症状を緩和・抑制するものです。「中和抗体薬」は、体内へ抗体を注入しコロナウイルスの表面に結合させて、細胞に侵入するのを防ぐ目的で使用します。
「抗ウイルス薬」「中和抗体薬」は、重症化リスク因子のある患者に対して重症化を防ぐ目的で投与され、かつ軽症の患者が対象です。
以下で、「抗炎症薬」「抗ウイルス薬」「中和抗体薬」それぞれのコロナ治療薬について解説します。
コロナ治療薬1.抗炎症薬
コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている抗炎症薬は「デキサメタゾン」「バリシチニブ」「トシリズマブ」の3種類です。
それぞれの対象者や特徴、注意点等を表でまとめましたのでご覧ください。
| 治療薬の成分名 | 販売名 | 対象者 | 特徴や注意点等 |
| デキサメタゾン | デカドロン錠等 | 重症感染症 | 抗炎症作用があるステロイド薬。重症感染症の治療薬として早い段階で承認されている。軽症の方に使用すると、症状が悪化する恐れがある。酸素吸入や人工呼吸器をつけるような重症感染症の方であれば、有害な炎症反応の抑制・予防効果が期待できる。腎不全の症状が増悪する恐れがあるため投与には注意が必要。 |
| バリシチニブ | オルミエント錠 | 中等症Ⅱ~重症 | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬で、関節リウマチやアトピー性皮膚炎などの治療薬として使用される。免疫反応の過剰な活性化を抑制する効果があり、新型コロナによる肺炎の治療に有効であると示唆されている。経口投与することで回復までの期間を1日短縮する。 |
| トシリズマブ | アクテムラ点滴静注 | 中等症Ⅱ~重症 | 炎症性サイトカインのIL-6の作用を抑制して炎症効果がある。新型コロナ患者は血中のIL-6濃度が上がっているとされ、トシリズマブの投与が治療に有効であるとされる。酸素投与を必要とするコロナ患者に対し、副腎皮質ステロイド剤とともに併用投与する。妊婦や授乳婦への投与も可能。 |
コロナ治療薬2.抗ウイルス薬
コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている抗ウイルス薬は「レムデシビル」「モルヌピラビル」「ニルマトレルビル・リトナビル」「エンシトレルビルフマル酸」の4種類です。
それぞれの対象者や特徴、注意点等を表でまとめましたのでご覧ください。
| 治療薬の成分名 | 販売名 | 対象者 | 特徴や注意点等 |
| レムデシビル | ベクルリー点滴静注用 | ハイリスクの軽症~重症 | 元々、エボラ出血熱の治療薬として開発されていた薬。ゲノムに作用し、ウイルスの複製を阻害する効果がある。コロナによる肺炎患者の回復までの期間を5日短縮する効果が報告されている。また、軽症者の入院や死亡リスクを抑制することがいくつかの研究から示唆されている。3日間の点滴治療が必要。 |
| モルヌピラビル | ラゲブリオカプセル | ハイリスクの軽症~中等症Ⅰ | 新型コロナウイルスの軽症患者に使える初の飲み薬。投与により入院・死亡を30%減少することが示唆されている。妊婦や授乳婦への投与は禁忌。服用中および服用後4日間は避妊が推奨される。 |
| ニルマトレルビル・リトナビル | パキロビッドパック | ハイリスクの軽症~中等症Ⅰ | 併用禁忌が多数あるコロナ治療薬。重症化リスクのある軽症の小児に対して適応となる。投与により、入院および死亡リスクを89%減少させることが示唆されている。腎障害時には調整した上で投与しなければならない。 |
| エンシトレルビルフマル酸 | ゾコーバ錠 | 軽症~中等症Ⅰ(症状の回復までの期間を1日短縮) | 新型コロナウイルスの治療薬として初めて緊急承認が適用された。酵素の働きを抑制してウイルスの増殖を抑える。投与により症状回復までの期間を1日短縮できると示唆されている。併用禁忌が多数あるため、医師・薬剤師に飲み合わせを確認することが必須。妊婦および授乳婦は禁忌である。 |
紹介した治療薬の中には併用禁忌となる薬が多数あるものや、妊婦・授乳婦への使用が禁忌とされているものがあります。医師・薬剤師の説明を十分に受け、正しく使用しましょう。
コロナ治療薬3.中和抗体薬
コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている抗ウイルス薬は「カシリビマブ・イムデビマブ」「ソトロビマブ」「チキサゲビマブ・シルガビマブ」の3種類です。
それぞれの対象者や特徴、注意点等を表でまとめましたのでご覧ください。
| 治療薬の成分名 | 販売名 | 対象者 | 特徴や注意点等 |
| カシリビマブ・イムデビマブ | ロナプリーブ注射液セット | ・ハイリスクの軽症~中等症Ⅰ・濃厚接触者の発症抑制 | 2種類の中和抗体を混ぜ点滴投与するカクテル療法により治療を行う。入院・死亡を70%減少させると示唆されている。濃厚接触者の発症抑制のためにも使用でき、32~81%まで発症割合を減少させると示唆されている。オミクロン株には使用不可。 |
| ソトロビマブ | ゼビュディ点滴静注液) | ハイリスクの軽症~中等症Ⅰ | ウイルスの変異が起きにくい領域に作用する治療薬。オミクロン株にも使用できるものの、亜種である「BA.2」には効果が低いという見解が示されている。投与により入院・死亡を79~85%減少させると示唆されている。 |
| チキサゲビマブ・シルガビマブ | エバシェルド筋注セット | ・ハイリスクの軽症~中等症Ⅰ(重症化・死亡を50%減少)・免疫抑制患者等の暴露前発症抑制(発症の割合を77%減少) | ウイルスが細胞に付着するのを防ぐことで効果を発揮する。免疫抑制患者等へウイルス暴露前に投与できる治療薬として、日本では初めて承認された。投与により発症割合を77%減少させると示唆されている。また、軽症~中等症Ⅰの患者へ投与することで、重症化および死亡を50%減少させることが示唆されている。 |
こうした薬の処方について、オンライン診療であれば自宅にいながら相談可能です。
特に、おうち病院「オンライン発熱・コロナ外来」なら、自宅で受診の上、薬を近くの薬局で受け取るか自宅に配送してもらうか選ぶこともできます。
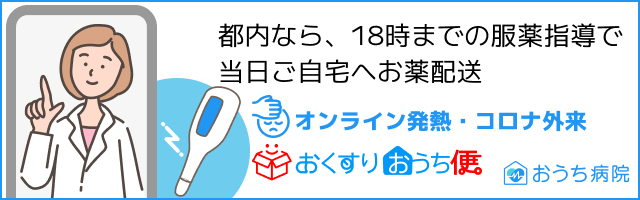
【抗炎症薬】コロナ治療薬を紹介
コロナ治療薬を種類別に詳しく紹介します。
抗炎症薬は、新型コロナウイルス感染症の重症化で起こる、過剰な免疫反応を抑制する働きがあります。
コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている抗炎症薬は「デキサメタゾン」「バリシチニブ」「トシリズマブ」の3種類です。
それぞれ対象患者や特徴、注意点などを詳しく見てみましょう。
①デキサメタゾン
デキサメタゾンは抗炎症作用や免疫抑制作用を持つ副腎皮質ステロイド薬で、さまざまな疾患に使用されています。
コロナ治療薬としては、重症患者の治療薬として2020年7月、早い段階で承認されています。酸素吸入や人工呼吸器をつけるような重症感染症の方であれば、有害な炎症反応の抑制・予防効果が期待できます。
ただし、軽症の方に使用すると症状が悪化する恐れがありますので、適切なタイミングでの投与が必要です。
また、腎不全の症状が悪化する恐れがあるため投与には注意が必要です。
②バリシチニブ
バリニシチブは、関節リウマチやアトピー性皮膚炎などの治療薬として使用されている、ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬です。
炎症や免疫機能に関わるサイトカイン(※1)の免疫活性化シグナル伝達において、重要な役割を果たすJAKを阻害します。これにより、免疫反応の過剰な活性化を抑制する効果があります。
新型コロナによる肺炎の治療にも有効とされ、コロナ治療薬としても2021年4月に承認されています。経口投与することで回復までの期間を1日短縮するとされています。
肺炎を起こすほどの中等症から重症患者に用います。
※1 サイトカイン:免疫細胞から分泌されるタンパク質で、細胞間の情報伝達や生理活性物質の総称
③トシリズマブ
トシリズマブは、炎症性サイトカイン(※2)のIL-6(インターロイキン-6)の過剰な働きを抑制して炎症を抑える効果があります。
新型コロナ患者は血中のIL-6濃度が上がっているとされ、トシリズマブの投与が治療に有効であるとされています。
酸素投与を必要とする中等症から重症のコロナ患者に対し、副腎皮質ステロイド剤とともに併用投与します。妊娠中や授乳育児中の女性への投与も可能です。
※2 炎症サイトカイン:炎症反応を促進する働きを持つサイトカインの一種。細菌やウイルスなどの病原体が体内に入ると分泌されて体を守る役割を担う。
【抗ウイルス薬】コロナ治療薬を紹介
ウイルスの増殖を抑えることで、症状を緩和・抑制する、抗ウイルス薬を紹介します。
コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている抗ウイルス薬は「エンシトレルビルフマル酸(販売名:ゾコーバ)」「レムデシビル」「モルヌピラビル」「ニルマトレルビル・リトナビル」の4種類です。
それぞれ対象患者や特徴、注意点などを詳しく見てみましょう。
①エンシトレルビルフマル酸(販売名:ゾコーバ)
エンシトレルビルフマル酸は、販売名をゾコーバと言います。
2022年2月に、新型コロナウイルスの治療薬として開発され、国内で初めて緊急承認が適用された薬です。酵素の働きを抑制してウイルスの増殖を抑える働きがあります。
投与により症状回復までの期間を1日短縮できると臨床試験で確認され、発表しています。軽症から、酸素投与が必要なほどの呼吸不全が見られない中等症患者に用いられます。
開発映像販売元の塩野義製薬株式会社発行の添付文書によると、併用禁忌が多数あるため、医師・薬剤師に飲み合わせを確認することが必須です。
他の疾患や持病で服薬中の薬がある方は、医療機関へ受診する際、処方してもらう前におくすり手帳を提出すると良いでしょう。
妊娠中や妊娠の可能性のある方、授乳育児中の女性へは、投与できません。また、腎機能又は肝機能障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者にも投与できません。
参照元:ゾコーバ錠添付文書|一般社団法人日本医薬情報センター(JAPIC)
②レムデシビル
コロナ治療薬として、世界で初めて承認され、日本でも2020年5月に承認第1号となった薬です。
元々、エボラ出血熱の治療薬として開発されていた薬です。ゲノムに作用し、ウイルスの複製を阻害する効果があります。そのため体内に入り込んだ新型コロナウイルスの増殖を抑える効果があるとされています。
コロナによる肺炎患者の回復までの期間を5日短縮する効果が報告されています。また、軽症者の入院や死亡リスクを抑制することがいくつかの研究から示唆されています。3日間の点滴で投与します。
持病を持っているか高齢等で、感染するとハイリスクがある軽症患者から、重症患者まで対応する薬です。
※3 ゲノム:DNAのすべての遺伝情報のこと。遺伝子(gene)と染色体(chromosome)から合成された言葉です。
③モルヌピラビル
2021年12月に承認された、新型コロナウイルスの軽症患者に使える国内初の飲み薬です。
持病を持っているか高齢等で感染するとハイリスクがある軽症患者から、酸素投与が必要なほどの呼吸不全は見られない中等症患者に用いられます。
新型コロナウイルスが体内で正常な遺伝情報をコピーする際、コピーエラーを起こしウイルスの活発な活動を減少させます。服用により入院・死亡を30%減少することが示唆されています。
妊娠中や妊娠の可能性のある方、授乳育児中の女性へは、投与できません。服用中および服用後4日間は避妊が推奨されています。
④ニルマトレルビル・リトナビル
ニルマトレルビル・リトナビルは、それぞれの役割と相互作用によってコロナ治療薬としての効果を発揮します。
ニルマトレルビルは、ウイルスの複製に必要なタンパク質の切断を行い、複製を抑制します。リトナビルは、CYP3A(※4)による代謝を阻害することによってニルマトレルビルの代謝を遅らせ薬物動態を改善します。
投与により、入院および死亡リスクを89%減少させると報告されています。
ただし、併用禁忌が多数あり処方の際には注意が必要です。腎障害時には調整した上で投与しなければなりません。
主に重症化リスクのある軽症の小児に対して適応する薬です。
※4 CYP3A4:薬物代謝やコレステロール、ステロイド、脂質の合成に関与するタンパク質です。薬物の代謝に重要な役割を果たします。
【中和抗体薬】コロナ治療薬を紹介
中和抗体薬は、体内へ抗体を注入しコロナウイルスの表面に結合させて、細胞に侵入するのを防ぐ働きがあります。
コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている中和抗体薬は「カシリビマブ・イムデビマブ」「ソトロビマブ」「チキサゲビマブ・シルガビマブ」の3種類です。
それぞれ対象患者や特徴、注意点などを詳しく見てみましょう。
①カシリビマブ・イムデビマブ
カシリビマブ・イムデビマブの2種類の中和抗体を混ぜ点滴投与します。2種類の抗体を混ぜて投与するためカクテル療法と呼ばれています。入院・死亡を70%減少させると示唆されています。
抗体が新型コロナウイルスの表面にあるスパイスたんぱく質に結合することで、増殖を抑制します。これにより、人の細胞に侵入するのを防ぎ、重症化を予防する働きがあります。
持病を持っているか高齢等で感染するとハイリスクがある軽症患者から、酸素投与が必要なほどの呼吸不全は見られない中等症患者に用いられます。
コロナ感染者の濃厚接触者の発症抑制のためにも使用でき、32~81%まで発症割合を減少させるされています。オミクロン株には使用不可です。
②ソトロビマブ
ソトロビマブは、体内で新型コロナウイルスに結合して細胞へのウイルスの侵入を防ぎます。それにより、悪化を阻止する効果が期待できます。
ウイルスの変異が起きにくい領域に作用する治療薬で、点滴により投与されます。
オミクロン株にも使用できるものの、変異株である「BA.2」には効果が低いという見解が示されています。投与により入院・死亡を79~85%減少させると示唆されています。
持病を持っているか高齢等で感染するとハイリスクがある軽症患者から、酸素投与が必要なほどの呼吸不全は見られない中等症患者に用いられます。
③チキサゲビマブ・シルガビマブ
新型コロナウイルス感染症及びその発症抑制のある薬です。筋肉注射を用いて投与します。
ウイルスが細胞に付着するのを防ぐことで効果を発揮します。免疫抑制患者等へウイルス暴露前に投与できる治療薬として、日本では初めて承認されました。
投与により発症割合を77%減少させると示唆されています。また、感染するとハイリスクのある軽症患者や呼吸不全のない中等症の患者へ投与することで、重症化および死亡を50%減少させることが立証されています。
対象となる患者は、感染するとハイリスクがある軽症患者から、酸素投与が必要なほどの呼吸不全は見られない中等症患者です。
コロナ治療薬でよくある質問
2023年5月から、新型コロナウイルス感染症は「5類感染症」となりました。5類感染症とは、感染症法が定める感染症の中で、総合的な観点から危険性が最も低いとされるものです。季節性インフルエンザや感染性胃腸炎、RSウイルス感染症などの一般的な感染症が5類に分類されています。
そのため、新規感染者の総数等を1日ごとに自治体から報告する全数把握から、1週間ごとに集計されて国立感染症研究所から報告される定点把握に切り替わりました。
5類になったとはいえ、コロナの脅威が去ったわけではありません。高齢者や持病のある方にとって重症化リスクがあり、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、コロナ治療薬に関して、行政に寄せられた質問を抜粋し、再編集してご紹介します。
治療薬は本当に安全?有効性は?
ご紹介してきたように、新型コロナウイルス感染症の治療薬は現在10種類承認されています。それらは、コロナ発生当時は存在しなかった薬や有効性がわからなかったものばかりであり、安全性や有効性について疑問や不安を感じている方もいることでしょう。
当初は「コロナに有効な既存薬があるのではないか」という視点で研究が進められていました。それと同時に、コロナ治療に特化した治療薬の開発・研究もスタートしました。現在日本で承認されている治療薬は、世界的に研究・開発をし、数多くの治験を行って統計的に効果があると認められたものです。そのため、正しく使用すれば安全であり、コロナ治療に有効であると考えられます。
ただし、治療薬によっては投与が禁忌となる方、併用禁忌の薬が存在します。医師はそれらを理解した上で処方していますので、ご安心ください。
市販薬は使用可能?
新型コロナウイルス感染症で辛いのは、意識が朦朧とするほどの高熱です。高熱による症状を少しでも緩和するために、市販の解熱剤を使用したいと考える方も多いのではないでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の熱症状緩和を目的とした市販の解熱剤の服用は可能です。用法用量を守っていれば問題はありません。
ただし、以下の場合はご注意ください。
・現在、他に服用している薬がある
・妊娠中、授乳中である
・高齢である
・胃や十二指腸潰瘍、腎機能低下のため治療中である
・薬の服用でアレルギー症状やぜんそくを起こした経験がある
・激しい痛み、高熱症状が重い
・症状が長く続いている
このようなケースでは、市販の解熱剤を服用する前に、主治医や薬剤師へご相談ください。
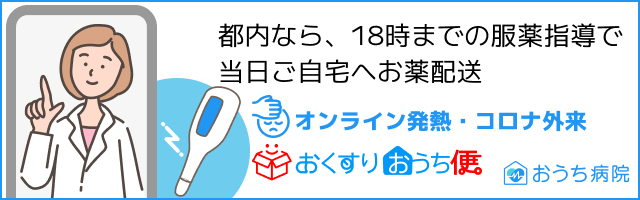
薬が足りないときは?
新型コロナウイルス感染症の症状が長引いてしまい、医療機関で処方してもらった治療薬が不足してしまうこともあるかもしれません。薬がないと高熱等で辛い思いをしてしまいますし、症状が悪化する恐れもあります。
薬が足りなくなる前に、自治体や医療機関に相談しましょう。自治体での対応については自治体ごとに異なります。オンライン診療で薬を配送してくれるケースもありますので、症状が辛い場合などは活用しましょう。
受け取りについては、同居者にお願いする、または置き配にするなどで対応可能です。
副作用が出たときはどうすればいい?
コロナの治療薬に限ったことではありませんが、どんな薬にも副作用が出る場合があるものです。
治療薬の投与によって体調が急に崩れたり、服用前とは異なる症状が現れたりした場合は、速やかに医師・薬剤師に相談しましょう。重大な副作用が出たにもかかわらずそれを放置すると、場合によっては命にかかわる可能性もあるためです。
療養解除のタイミングはいつ?
治療薬を使用して症状が軽快したものの、いつから療養解除となるのかわからない方も多いのではないでしょうか。病院受診時に医師から説明を受けたとしても、辛い療養生活の中で忘れてしまうこともあるかもしれません。
入院していない方の場合、新型コロナウイルス感染症の症状が発症した日から7日間経過し、症状軽快後24時間が経過している場合は、8日目から療養解除が可能とされます。
ただし、発症日から10日間が経過するまでは感染リスクが残存しています。そのため、健康状態の確認や検温、外出時のマスク着用などを行って、感染予防行動を自主的に行うことが推奨されています。
コロナの治療薬の処方を自宅で受け取るなら、「おうち病院 オンライン発熱・コロナ外来」
急な高熱など、新型コロナウイルスが疑われる症状があれば、なるべく早く、医療機関を受診して治療薬を処方してもらいましょう。
しかし、「高熱が出ていて外に出るのが辛い」「人との接触は避けたい」と思う方もいらっしゃることでしょう。「近くに発熱外来がない」「高熱患者を受け入れてくれない」といったケースもあるかもしれません。
そのような場合に活用したいのが、「おうち病院 オンライン発熱・コロナ外来」です。スマホやPC、タブレットなどの端末を用いて、自宅にいながら医師の診察を受けられます。24時間いつでも予約できますので、急な発熱でも安心です。
おうち病院なら、
✅ 通院時間や待ち時間が不要なので体調が悪い時でも安心受診
✅ 感染リスクのある病院に行かずに診察を受けられる
✅ 検査キットの陽性画像があれば、抗ウイルス薬(ゾコーバ、ラゲブリオ、パキロビット等)の処方も可能
✅ 朝8時〜夜22時まで診察可能!平日夜間・土日祝日いつでも受診可能
✅ 予約時間どおりに診察開始だから、朝の準備中・仕事の合間・帰宅後にも受診可能。
✅ 処方せんは指定薬局へ自動送信! 全国6,900店舗の薬局で受け取れるから便利
✅ 自宅配送サービス「おくすりおうち便」もあるので、薬局に行く時間がなくても安心
✅ 保険診療可能
診察後、処方箋は指定した薬局に自動的にFAX送信されますので、病院に行くことなくコロナの治療薬を受け取れます。コロナの症状で辛いなら、ぜひ「おうち病院 オンライン発熱・コロナ外来」をご利用ください。