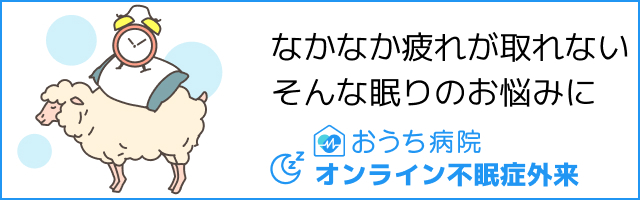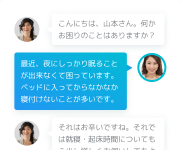睡眠トラブルを抱えていると、著しく日常生活に支障をきたしてしまうことがあります。適切な睡眠薬を用いて治療していく必要があります。
治療するにあたり、睡眠薬はどこで処方してもらえるか、保険はきくか、オンラインは可能かなど、多くの疑問を持っているのではないでしょうか。
本記事では、睡眠薬の処方について詳しく解説します。あなたの疑問が解決すれば幸いです。
目次
睡眠薬はどこで処方してもらえる?
睡眠薬は、症状や不眠の原因によって受診する科が異なります。ご自身の不眠症の原因がどこにあるか探りながら、確認してみましょう。
心療内科・精神科
ストレスや緊張・不安が原因と思われる場合は、心療内科・精神科を受診し、睡眠薬の処方をしてもらいます。
心療内科は、心の不安定が原因で身体に現れる症状について治療を行います。不眠症だけでなく、イライラや落ち込み、不安・緊張の結果、身体に影響を及ぼした症状に重点を置き、カウンセリングや症状の緩和に向けた薬物療法を行うことが多いです。
精神科は、心の病(うつ病や不安障害、パニック障害など)に対する治療が中心です。必要に応じて、抗うつ薬や抗不安薬、精神安定剤等を処方し、心理療法(認知行動療法など)が行われることもあります。
睡眠外来・不眠外来
睡眠トラブルによる悩みに対し、より専門的な診断や治療を受けることができる「睡眠外来」「不眠外来」で睡眠薬の処方が可能です。
睡眠外来であれば、睡眠に関する検査や相談により、不眠症以外の病気に関しても専門的な治療が可能です。
例えば、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)、ナルコレプシー(突然の睡魔や昼間の過度な眠気)、過眠症など、疾患が見つかった時その治療を行います。
婦人科
妊娠・出産に伴う睡眠トラブル、または月経周期等に関連して睡眠トラブルが起きていると思われる場合は婦人科でまず相談しましょう。
特に、妊娠・出産・授乳期では処方できない睡眠薬もあるため、専門的な知見が必要です。
女性ホルモンのバランスの変動は、自律神経のバランスを崩し、覚醒と睡眠をつかさどるホルモンのバランスも崩れることがあります。例えば、PMSの症状のひとつとして不眠または過眠症状が現れる方もいます。
また更年期障害では、女性ホルモンの分泌量が減少することで、寝汗やほてり(ホットフラッシュ)、気分の浮き沈みが激しい、疲れやすいといった症状が現れるほか、不眠に悩む方もいます。
これら女性ホルモンに関連する場合、婦人科への受診をおすすめします。
内科
内科でも睡眠薬の処方が可能です。
原因がわからない時は、ひとまず主治医かなじみのある内科へ相談する、という手段があります。専門的な治療が必要な場合は適切な科を紹介してくれるでしょう。
また、不眠症の原因の一つには、一時的な生活習慣の乱れがあります。
多忙によりストレスや過度な疲労がたまっている時、緊張が強い時、生活リズムが乱れている時、睡眠薬治療と並行して生活習慣を見直し、ストレス管理をすることで改善するケースがあります。
オンライン睡眠外来・不眠外来
オンライン睡眠外来、または不眠外来でも睡眠薬の処方が可能です。
スマートフォンやタブレット、またはパソコンで、ご自宅など好きな場所から好きな時間に受診することが可能です。そのためスキマ時間で済ませることができ、プライバシーも保たれます。
不眠症に悩み、病院に行きたいけど、多忙で通院する時間がない、病院に行くのは抵抗がある、プライバシーが心配、など通院に対してハードルが高いと感じる方は、こちらがおすすめです。
詳細は下記でも解説しています。
参考:不眠症で病院に行くなら何科?原因別に最適な診療科を解説 |オンライン診療サービス おうち病院
【通院?オンライン?】睡眠薬の処方方法を比較
通院とオンライン、結局どっちがいいのでしょうか?比較して表にまとめました。参考にして、ご自身の都合や状況に応じて良い方を選択してみましょう。
| 通院(対面診療) | オンライン診療 | |
| 処方の薬を受け取る方法 | ほとんどの場合受診した病院で薬は受け取れない。医師が処方箋を発行、薬局で薬を受け取る | 受診したオンラインクリニックで処方箋を発行しお住まいの地域で薬を受け取るか、直接自宅へ配送。 |
| 薬局での待機 | あり | 直接自宅へ配送を選択すると、待機時間なし |
| 処方する睡眠薬の限定 | なし | 厚生労働省の指針により、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬など、依存性の高い薬剤の初診でのオンライン処方は原則として認められていない |
| 処方後の異常が見られた時または疑問・質問がある時 | 再度受診予約など手間がかかる | 365日24時間オンライン上で相談ができるサービスがある |
| プライバシー | あまりない | 守られている |
| 他の患者との接触 | あり | 薬の自宅配送を選択した場合なし |
| 時間と距離の制約 | あり | なし |
オンラインは、多忙な方や通院が困難な方、心療内科・精神科受診へのハードルが高いと感じる方におすすめの手段です。便利であるとともに、プライバシーが守られます。
一方で、厚生労働省の指針により、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬など、依存性の高い薬剤は、初診でのオンライン処方は原則として認められていないため、処方することができません。
しかし、近年では副作用や依存性、離脱症状などの課題を持つ睡眠薬以外に、非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬やオレキシン受容体拮抗薬、メラトベル(メラトニン錠)なども多く開発されています。
依存性や副作用のリスクが低い薬、覚醒と睡眠の体内の仕組みやリズムにアプローチして自然な眠りへと導いてくれる薬が多く発売されています。そのような薬の処方はオンラインで可能です。
オンラインで、まずは気軽に相談という選択肢も良いのではないでしょうか。
処方される睡眠薬は保険が適用される?
睡眠薬の処方は、保険適用されるかどうか気になるのではないでしょうか。実は、保険適用される場合とされない場合があります。確認してみましょう。
保険適用の条件
睡眠薬の場合、医師の診断と医療機関での処方では保険適用となります。
不眠症や睡眠障害と診断された場合に、治療目的で処方される睡眠薬は、基本的に保険適用となります。医師が症状や必要性を判断し、適切な睡眠薬を処方します。
保険適用の場合、自己負担割合に応じて、医療費の1割~3割を負担します。
睡眠薬の種類や量によって費用は異なりますが、比較的安価で処方されることが多いです。
保険適用されないケース
保険適用されないケースは、以下3つあります。
保険適用外でも活用する価値があるか、自分に必要かどうかは医師に相談のうえ選択しましょう。
①医師が必要と認めない場合
軽度の不眠や、医師が睡眠薬の必要性がないと判断した場合、保険適用外となることがあります。この場合、患者が睡眠薬を強く希望する場合でも、医師の判断が優先されます。
②美容目的やパフォーマンス向上目的の場合
美容目的や一時的な睡眠不足を補うなど、治療目的以外での使用は、保険適用外となります。また、リラクゼーション目的のものやセラピストによる施術、いわゆる自費診療によるカウンセリング等も保険適用外となります。
③市販薬や個人輸入
薬局などで購入できる市販の睡眠改善薬やサプリメント、個人輸入した睡眠薬は、保険適用外です。
処方される睡眠薬の種類
処方される睡眠薬の種類について、詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。
入眠をサポートする睡眠導入剤
入眠困難を改善するのが睡眠導入剤です。寝つきが悪く入眠が困難な方向けです。
布団に入って30分以上眠れない方、寝ようと思えば思うほど目がさえてしまう方などが該当します。
睡眠薬は、睡眠全体をカバーするのが基本ですが、睡眠導入剤は特にスムーズな入眠にフォーカスした薬です。作用時間は2~4時間程度と、短時間で薬が体から抜けるため、朝まで作用が持続してしまう持ち越し効果(眠気やだるさなどが残る症状)の心配は低いと言えます。
主な睡眠導入剤は、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬(超短時間型)のマイスリー、アモバン、ルネスタなど、ベンゾジアゼピン系睡眠薬のハルシオンがあります。
依存性が比較的少ないとされています。
睡眠の質を改善する睡眠薬
浅い眠りで熟睡できない方、夜中に何度も目が覚めてしまう方、早朝に目が覚めてしまう方などにおすすめの、睡眠の質を改善し、熟睡をサポートする睡眠薬は、睡眠導入剤以外の睡眠薬全般です。
症状や、効き目によって強くしたり弱くしたり、睡眠薬の種類や量を医師が判断します。
睡眠の質を改善し、睡眠全般をサポートする睡眠薬は、以下の通りです。
| 睡眠薬の種類 | 半減期 | 薬品名(一般名) |
| オレキシン受容体拮抗薬 | ベルソムラ 12時間 デエビゴ 30時間 クービビック8時間 | ・ベルソムラ(スボレキサント) ・デエビゴ(レンボレキサント) ・クービビック(ダリドレキサント) |
| メラトニン受容体作動薬 | 1時間程度 | ・ロゼレム(ラメルテオン錠) ・メラトベル(メラトニン錠) |
| ベンゾジアゼピン系睡眠薬 | 短時間型(6~10時間) | ・レンドルミン(ブロチゾラム) ・リスミー(リルマザホン塩酸塩水和物) ・エバミール、ロラメット(ロルメタゼパム) ・デパス(エチゾラム) ・サイレース(フルニトラゼパム錠) |
| 中間型(21~28時間) | ・ベンザリン、ネルボン(ニメタゼパム) ・ユーロジン(エスタゾラム) | |
| 長時間型 (36~85時間) | ・ドラール(クアゼパム) ・ダルメート、ベノジール(フルラゼパム塩酸塩) |
※半減期とは、薬の血中濃度が半分になる時間のこと。半減期と作用時間はイコールではないものの、半減期が短ければ薬が体から抜けるのも早い。
心の安定を促す精神安定剤・抗不安薬
心の不安やイライラ、緊張等心の不安定さが原因と思われる不眠症の場合、精神安定剤や抗不安薬を服用する場合があります。
心の安定を促し、リラックスへと導くことで、自然に健全な眠りへと導きます。そのため不眠症治療にも多く利用されています。
主に心の安定にフォーカスした不眠治療の薬は以下の通りです。
| 睡眠薬の種類 | 薬品名(一般名) |
| ベンゾジアゼピン系睡眠薬 | レンドルミン(ブロチゾラム) リスミー(リルマザホン塩酸塩水和物) デパス(エチゾラム) |
| 漢方薬 | 加味帰脾湯(かみきひとう) 酸棗仁湯(さんそうにんとう) 抑肝散(よくかんさん) 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう) |
精神疾患に抗うつ薬・抗精神薬
精神疾患が原因で不眠を伴う場合があります。精神疾患の治療が優先され、抗うつ薬や抗精神薬で、不眠にも効果が期待できる薬を用います。
一部の抗うつ薬は、特定の脳内受容体に作用して脳の働きを鎮め、睡眠の質を向上させます。その鎮静効果から「鎮静系抗うつ薬」と呼ばれています。抗精神病薬も、不眠症治療薬ではありませんが、睡眠の質を改善する効果を与えることがあります。
抗うつ薬や抗精神薬としても使用される睡眠薬は、トラゾドン(トラゾドン塩酸塩錠)です。
抗うつ薬や抗精神薬と睡眠薬を併用する場合には注意が必要で、睡眠薬の中には併用禁忌(併用してはいけない薬)も存在します。
処方される睡眠薬の作用メカニズム
睡眠薬の作用の仕組みは大きく分けて2種類あります。どちらが向いているかは、医師の判断ですが、希望を伝えることは可能です。確認してみましょう。
脳の活動を抑える脳機能抑制型睡眠薬
脳の活動を抑えることで、眠気を促すタイプの睡眠薬です。従来の薬はこれが主流でした。
興奮を鎮める脳の神経伝達物質GABAの働きを高めることで、脳の活動を強制的に抑えます。それにより催眠作用を発揮します。
脳の機能を抑える脳機能抑制型睡眠薬は、主にベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系があります。
強い催眠作用があることが特徴です。同時に重大な副作用や依存性、耐性、薬を中止した時の離脱症状(禁断症状)等の課題があります。
自然な眠りを促す生理的睡眠促進型睡眠薬
体内の睡眠・覚醒リズムに関与する物質の働きを調整し、自然な眠りを促す睡眠薬です。
比較的新しい薬が多くあり、覚醒と睡眠の体内のメカニズムにアプローチするため、自然な眠りに近く、副作用や依存性・耐性・離脱症状のリスクが低いものもあります。
主な自然な眠りを促す生理的睡眠促進型睡眠薬は、以下の通りです。
・メラトニン受容体作動薬
体内時計(概日リズム)に関係する、夜分泌される睡眠ホルモン「メラトニン」の受容体に作用してその働きを高め、睡眠の質の改善をサポートする睡眠薬です。
・オレキシン受容体拮抗薬
覚醒を維持する脳内の神経伝達物質オレキシンの働きを阻害することで、覚醒状態からリラックスへと導き、自然に近い眠りへと導く睡眠薬です。
【受診の目安】睡眠薬を病院で処方してもらう?市販薬で済ませる?
睡眠薬の処方をしてもらうか、市販薬で様子を見るレベルか、迷うこともあると思います。現在の不眠の悩みと照らし合わせて確認してみましょう。
一時的な不眠の悩みなら市販薬で様子を見よう
不眠症状が、一時的なものなら生活習慣の改善や市販薬で、様子を見るのも良いでしょう。
以下のような症状の場合は様子見で問題ありません。
- 一時的な環境変化による寝つきの悪さ
- 一時的なストレスによる寝つきの悪さ
- 軽い時差ボケによる睡眠リズムの乱れ
- 週末の寝坊などによる一時的な睡眠リズムのずれ
- ごくたまに起こる、軽度の寝つきの悪さ
市販薬の他、メラトニンなどのサプリメント、リラックス効果のあるハーブティーやアロマもおすすめです。
また、下記に該当する方は市販薬の購入はせず、受診をおすすめします。
- 他の病気で治療中の方や、他の薬を服用している方
飲み合わせによっては危険を伴います。必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合
いびきがひどい、日中の眠気が異常に強いなどの症状がある場合は、専門医の診察が必要です。
- 精神的な問題(不安、抑うつなど)が不眠の原因となっている可能性がある場合
心療内科か精神科を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
日常生活に支障をきたしているなら睡眠薬の処方がおすすめ
日常生活に支障をきたしている場合はおもいきって受診し、睡眠薬を処方してもらいましょう。
不眠症状が1~2週間続いているならただちに受診をおすすめします。
受診のタイミングや症状は以下を参考にしてください。
- 市販薬を数日~1週間程度使用しても、全く効果がない、または効果が薄い
- 日中の強い眠気や倦怠感で仕事や家事に集中できない(集中力や記憶力の低下・イライラ・気分が落ち込む・頭痛や体調不良が続く)
- 不眠の症状が長期間(1ヶ月以上)続いている
- これまでになかったタイプの不眠が現れた
- 市販薬の使用によって、予期しない副作用が現れた
睡眠薬の処方箋は誰でも受け取れる?
睡眠薬の処方箋は実は誰でも受け取れるわけではありません。
投薬ができない人と注意が必要な人について解説します。
睡眠薬を処方できない患者(禁忌)
睡眠薬の種類にもよりますが、以下の患者は睡眠薬の投薬ができない場合が多いです。
- 重度の呼吸器疾患
睡眠薬は呼吸抑制作用があるため、重度の睡眠時無呼吸症候群や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患を持つ患者さんには、慎重な投与が必要または処方できない場合があります。
- 重度の肝機能・腎機能障害
睡眠薬の代謝や排泄に影響を与えるため、重度の肝機能・腎機能障害を持つ患者さんには、投与量の調節が必要または処方できない場合があります。
- 閉塞隅角緑内障
一部の睡眠薬は眼圧を上昇させる可能性があり、閉塞隅角緑内障の患者さんには禁忌となる場合があります。
- 重症筋無力症
睡眠薬は筋弛緩作用があるため、重症筋無力症の患者さんには症状を悪化させる可能性があります。
- 妊娠中・授乳中
胎児や乳児への影響が懸念されるため、妊娠中・授乳中の女性には、原則として睡眠薬の投与は推奨されません。
睡眠薬の処方に注意が必要な患者
また、以下の患者には、睡眠薬の投薬は慎重に行うべきです。
- 高齢者
高齢者は薬の代謝や排泄機能が低下しているため、副作用が出やすく、意識の混乱やふらつき、転倒のリスクも高まります。
- うつ病などの精神疾患
睡眠薬はうつ病の症状を悪化させる可能性があり、慎重な投与が必要です。抗うつ薬との併用、または不眠効果も期待できる抗うつ薬が必要になる場合があります。
- 薬物依存の既往歴
睡眠薬には依存性があるため、薬物依存の既往歴がある患者には、慎重な投与が必要です。
- 他の薬物との併用
他の中枢神経抑制作用のある薬物との併用は、相互作用により副作用が強く出る可能性があり、危険です。
セルフケアで睡眠の質を高めることも重要
処方薬治療だけでなく、セルフケアも重要です。
睡眠の質を高める日常生活改善について解説していきます。意識して実践してみてください。
寝室の環境整備
寝室や寝具の環境をまずは整えましょう。
落ち着いた色合いのインテリア(アースカラー)はおすすめです。また、就寝時の照明はできるだけ低照度にし、昼光色(青白い光)は目が覚めやすいため、暖色系の光(オレンジ系など)にします。
ブルーライトはメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑え、体内時計のバランスを崩してしまうと言われています。なるべく寝室にスマホやタブレットは持ち込まず、就寝の1時間前くらいから見ないようにしましょう。
生活習慣の改善
生活習慣の見直しは重要なステップです。仕事の都合等で夜型になってしまう方や不規則な生活の方は、特に意識しましょう。規則正しい生活リズムが体調を整えます。
また、朝陽をあびる事で体内時計(概日リズム)がリセットされ、夜のメラトニン分泌を促します。起床後はカーテンを開けましょう。散歩もおすすめです。
なお、就寝前の食事は、胃腸に負担をかけ睡眠を妨げます。夕食は就寝の3時間前までに済ませて、消化の良いものを意識しましょう。
適度な運動
適度な運動は、昼の活動を活発にし、夜の熟睡を促します。
有酸素運動は、寝つきが良くなり、深い睡眠を促す効果も期待できます。日中の定期的な運動を習慣にするとよいでしょう。激しい運動をいきなりするのではなく、軽い運動から始めます。メラトニン生成も兼ねてウォーキングやランニングなども良いでしょう。
ただし、就寝1時間以内の運動は、脳が興奮状態になり入眠を妨げますので、控えましょう。
就寝前には飲酒・喫煙・コーヒーを避ける
就寝前は、飲酒・喫煙・コーヒーを避けましょう。これらの摂取は睡眠の質を低下させます。
アルコールは一時的にリラックスできるものの、眠りが浅くなり睡眠の質を悪化させます。また、利尿作用により夜間のトイレで目が覚めやすくなります。
タバコに含まれるニコチンには覚醒作用があります。就寝1時間前から喫煙は避け寝室では吸わないようにします。カフェインは摂取後3~5時間効果が持続するため、カフェインを含むコーヒー・緑茶等の夕方以降の摂取はできるだけ控えましょう。
リラックス・リフレッシュをする
ストレスをためないようにしましょう。
仕事などで常に緊張状態にある人は、脳が興奮している状態なので、リラックスできる時間を作ります。
ストレスやイライラ、緊張状態や不安を抱えてしまう場合、好きなことをしてリフレッシュできるように、ストレス管理をしていきます。
入浴はシャワーよりバスタブにつかると効果的です。また、アロマやハーブの活用も効果的です。おすすめはラベンダー、カモミール、レモンバームです。
就寝前は考え事をしない
夜寝る前に布団やベッドの入るとあれこれ浮かんできて眠れない方も多いかと思います。仕事のことや不安があるとどうしても考えてしまいますね。あれこれ考えると興奮・覚醒してしまいます。
しかし、心配事をするより振り返るなら良かった事、自分へのねぎらいを意識してみましょう。自分へのねぎらいは、リラックス効果をもたらします。最初は難しいかもしれませんが、リラックスのアイテムを実践しながら思い浮かべてみてください。
不眠症の処方薬なら「おうち病院 オンライン不眠症外来」
不眠症の治療相談や薬の処方には、「おうち病院 オンライン不眠症外来」がおすすめです。
おうち病院なら、
✅通院時間や待ち時間が不要なので体調が悪い時でも安心受診
✅初診から保険診療可能
✅朝8時〜夜22時まで診察可能 平日夜間・土日祝日いつでも受診可能
✅スキマ時間で受診できるから、朝の準備中・会議の合間・夜のリラックスタイムにも◎
✅予約時間どおりに診察開始だから、朝の準備中・仕事の合間・帰宅後にも受診可能。
✅処方せんは指定薬局へ自動送信 全国6,900店舗の薬局で受け取れるから便利
✅自宅配送サービス「おくすりおうち便」もあるので、薬局に行く時間がなくても安心
近年、依存性の高い睡眠薬の使用について心配の声を聞くことも少なくありません。そのため、「おうち病院 オンライン不眠症外来」では患者の安全を考慮し、依存性の高いベンゾジアゼピン系睡眠薬(ユーロジン、ドラール、ハルシオンなど)の処方を行わない方針を取っています。
代わりに、ラメルテオン(ロゼレム)やレンボレキサント(デエビゴ)など、より依存性の低い薬剤を中心に処方しています。
睡眠薬をどこで処方してもらうかは、自分の症状や状況に合わせて選択しよう
睡眠薬をどこで処方してもらうかは、症状や体質によって違います。
自分の症状を振り返ってみて、適切な科を受診しましょう。不眠症だけでなく、思わぬ病気が隠れている可能性もあります。しかし自分で判断がつかなくても、内科やオンライン等でまずは相談することも可能です。
また、状況に応じて対面診療かオンライン診療の選択肢があります。
通院のハードルが高いと感じて不安な時は、サクッと相談できるオンラインでまずは相談してはいかがでしょうか。